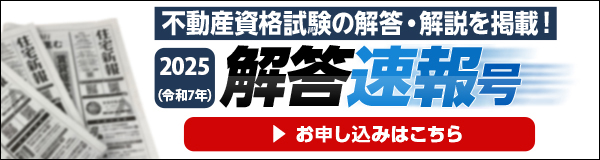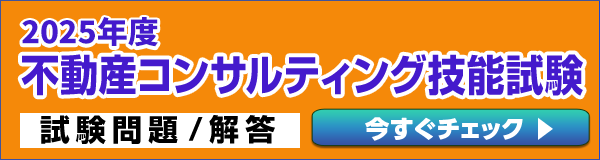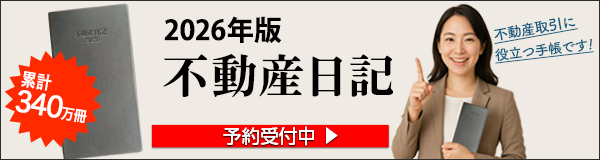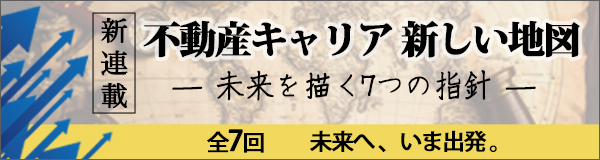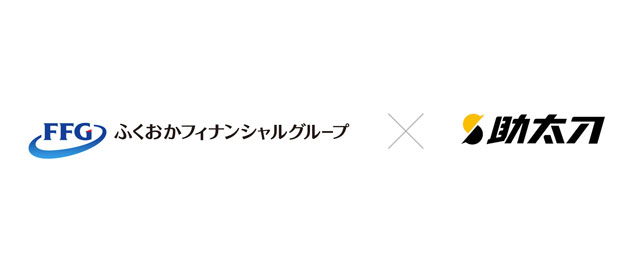社説「住宅新報の提言」 記事一覧
-
社説 レインズ、ステータス管理導入 消費者目線を重視しよう
新年早々、全国四の不動産流通機構(レインズ)で、取引状況の登録制度導入と売却依頼主専用確認画面の提供が始まった。売り物件が公開中なのか、購入申込み書を受け付けている段階か、あるいは売主の都合で一時紹介(続く) -
社説 16年の住宅・不動産業界 〝本気度〟上げる1年に
新たな1年が始まった。干支の「申」は、「伸ばす」を表し、「実が成熟して固まっていく」という意味もあるようだ。住宅・不動産業界ではここ数年、これまで通りの既定路線にはない新たな動きが見られている。人口(続く) -
社説 分譲マンションの傾き問題 原因の早期究明と説明が必要だ
外的要因がないとすれば、住宅が傾く原因は設計ミスか施工不良のいずれかである。工事を依頼した施主には、発注条件によっては一定の責任が出てくる場合もあるが、直接的な責任はそれを請け負った設計者か建設会社(続く) -
社説 「3世代同居」推進に期待 子育てを多面的にサポート
安倍首相が「3世代同居の推進」を打ち出した。従来、政府はこのような個人のライフスタイルに関わることを政策目標にすることはなかった。しかし、日本の少子高齢化問題は、もはやそのようなことを言っておられな(続く) -
社説 予断を許さない住宅市場 増税後を見据えた布石を
15年度中間決算期を迎え、特殊要因を除けば新築住宅の請負が回復傾向にある大手各社の受注状況が明らかになった。政府により経済対策の一環として住宅取得支援策が打たれたこともあって、8%への消費税増税に伴い長(続く) -
社説 注目度高まる「民泊」 参入の際は「プロ」の手本を
このところ、「民泊」の文字が様々なメディアで飛び交っている。民間住宅の空き部屋を有効活用する手段、もしくは昨今話題になっている「老朽空き家」の利活用につながるのではないかと不動産業界内でも注目が高ま(続く) -
社説 問われる一人ひとりの責任 マンション施工、改ざん問題
起きてはならないことが起きてしまった。基礎杭データ改ざんによる建設工事。故意によるものとしたなら、怒りを通り越した感情が沸き起こる。「安全・安心」の確保を生命線とする建設業界、そして住宅・不動産業界(続く) -
社説 マンション市場の主役は 勤労者に魅力的な商品を
新築マンションの売れ行きがいい。首都圏の場合、発売戸数は前年を下回っているが、月間契約率は70%を超える水準を保ち、大きな減速要因は見当たらないように見える。大手不動産の経営トップも用地高、建築費高な(続く) -
社説 高齢化進む首都圏郊外 都心にない魅力づくり急げ
国立社保障・人口問題研究所の資料によると、首都圏の高齢化率は20年に26%、30年に29%、40年に35%、50年に39%と高まっていき、それ以降は高齢者比率がほぼ定着し、60年になっても40%と推測されている。つまり、首(続く) -
社説 16年度税制改正議論が本番 住宅取得の固定資産税軽減拡大を
来年度の予算要求と税制改正要望が各省庁からこのほど発表され、年末の税制改正大綱とりまとめに向けた税制改正議論が本番を迎える。住宅税制の来年度のひとつの争点になると言われているのが、「新築住宅にかかわ(続く) -
社説 必要度高まる後見制度 知識を深める時期が来た
後見制度のスタートから15年が経過した。知的障害や認知症といった判断能力が不十分な人に代わって、後見人が財産管理や法律行為などを行うものだ。高齢化がますます進む我が国において、利用者は必然的に増えるこ(続く) -
社説 変わり目に来た不動産流通業 IT時代の在り方考えるとき
ストック活用時代である。国土交通省が中古住宅流通・リフォーム市場の倍増方針を掲げて以来、重点課題の一つとして中古住宅市場活性化策を推進中であることに加え、自民党政務調査会中古住宅市場活性化小委員会((続く) -
社説 地方創生に不可欠 「地域主権型道州制」の検討を
地方創生の動きが本格化している。政府が6月末に閣議決定した地方創生基本方針に日本版CCRC構想の推進が盛り込まれたのもその一つだ。 山崎史郎内閣官房まち・ひと・しごと創生本部統括官は同構想について「施設(続く) -
社説 27年路線価 上昇基調が拡大 地価の安定を豊かさに
相続税、贈与税を算定する土地の評価額の基準となる全国の路線価がこのほど、国税庁から発表された。全国の平均値は0.4%下落となり、前年に引き続いて下落したものの、下落幅は0.3ポイント縮小した。都道府県庁所(続く) -
社説 空き家問題は住宅政策 隣家への売却に優遇策を
空き家問題がクローズアップされて久しい。そこでは常に空き家が820万戸存在すると流布されている。しかし、この中には賃貸用429万戸、売却用31万戸などが含まれている。問題となっているのは「その他の住宅」とさ(続く) -
社説 標準管理規約の改正 「コミュニティ条項」削除に違和感
マンション管理組合にとって、管理運営内容を定める上で大きな指針となる標準管理規約。その改正が検討されているが、規約の中から「コミュニティ条項を削除する」という方向で話が進んでいる。その検討に対して、(続く) -
社説 不動産各社を待ち受けるもの 人口減少社会見据えた備えを
大手不動産会社の3月決算は、収益で過去最高決算が相次ぐなど、業績は安定成長軌道を歩き始めたように見える。分譲住宅が比較的堅調だったほか、オフィス市況が改善。更に不動産投資ブームを背景に投資家向け分譲(続く) -
社説 地方創生待ったなし 格差放置すれば日本全体が衰退
「東京一極集中」の是正が国の方針として正式に決定された(まち・ひと・しごと創生長期ビジョン14年12月)にもかかわらず、肝心の国民が本気にしていないフシがある。20年の東京オリンピック開催を背景にインフラ整(続く) -
社説 低金利と贈与の追い風 実需が育つ住宅市場に
消費税増税を乗り越えた住宅・不動産市況だが、今ひとつ回復の波に乗りきれていない。比較的、販売好調を維持しているのが富裕層や高所得層を主な対象とした高価格帯の住宅マーケットで、このマーケットに焦点をあ(続く) -
社説 鑑定士試験制度の見直し 質の向上で魅力を伝えよ
難関とされる不動産鑑定士の試験制度が変わりそうだ。国土交通省は昨年末から委員会を設置して、試験のあり方について検討を重ねてきている。理由は減少を続けている不動産鑑定士の受験生を回復することだが、そこ(続く)