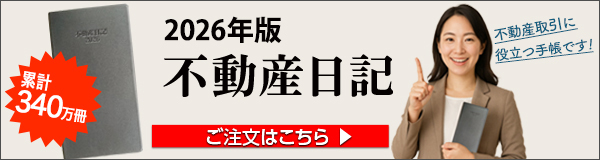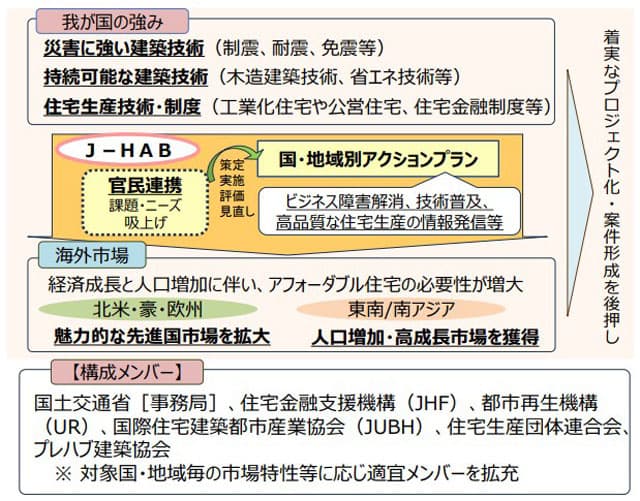後見制度のスタートから15年が経過した。知的障害や認知症といった判断能力が不十分な人に代わって、後見人が財産管理や法律行為などを行うものだ。高齢化がますます進む我が国において、利用者は必然的に増えることになるだろう。
当然のことながら、住宅・不動産業界にも大きな影響が及ぶと考えられる。高齢者が持っている代表的資産は、「預貯金」「株」「保険」、そして「不動産」。制度普及を目的に活動する一般社団法人「後見の杜」の調査によると、後見制度を利用した居住用不動産の売却件数は年々増えている。04年に1355件だったものが、13年には6222件に拡大した。16年には約1万件となる試算だ。オリンピック後の23年には2万5000件程度にまで増加する。
取引の現場からも、「主人が認知症だが、どのような方法で所有不動産を処分すればよいのか分からない」といった内容の相談を受けたという声が、以前にも増して聞かれるようになった。ファイナンシャルプランナーや保険・銀行従業者の間では、この制度に対する理解度が上がっているという。積極的な研修参加も見られるようだ。不動産業界も、取引の円滑化のために後見制度の知識を深めていくべき時期に来ている。
制度の目的は
言葉の響きなどからして、「難解な制度なのではないか」と懸念する不動産事業者は多いだろう。家庭裁判所なども介在するため、法律の専門家などに任せたほうが安心といった考え方も生まれがちだ。ただ、後見制度の主たる目的は、後見される人のことを考え、本人に代わって生活の質を上げる様々な行為を行うことにある。そこには法律のプロや素人といった問題は生じない。実際、後見人の多くは被後見人の親族がなっている。
不動産事業者が、後見人になる必要はない。要は、まだまだ馴染みの薄い後見制度について、相談者に対して分かりやすく説明することができるかどうかだ。そのことは、今後更に必要度が高まる後見制度を、広める役割を果たすことにもなる。もちろん、自身の不動産取引のビジネスチャンスにつながることは、言うまでもない。
ただ、後見制度がすべてに対して万能かといえば、そうとも言えない。費用や手間の問題から、制度を利用しないほうがよい場合もあるという。相談者を取り巻く環境は千差万別。様々な相談に対応できるようになるためにも、研鑽は必要だ。
この4月から宅建士となり、不動産事業者には地域の「よろず相談処」としての機能が以前にも増して求められている。後見制度の理解を深めることは、その期待に応える大きな武器となるはずだ。