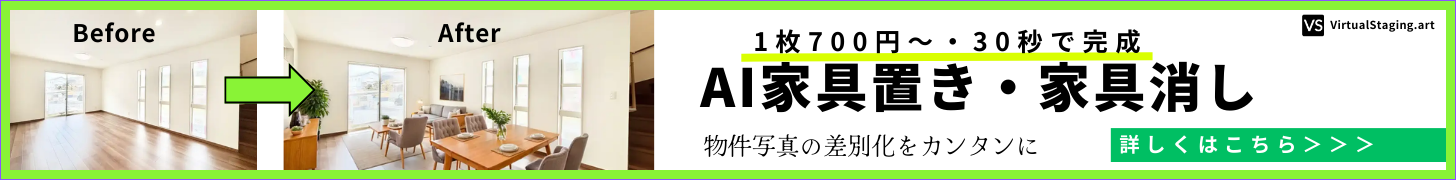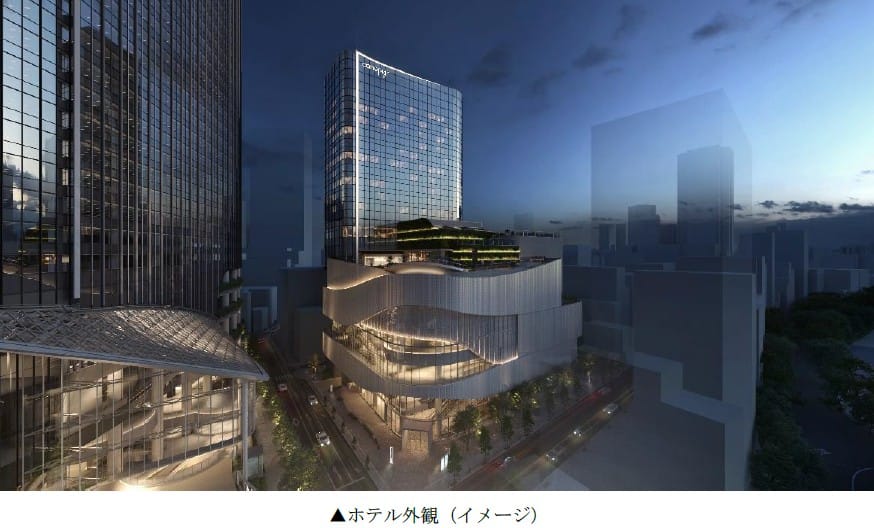総合
-
東京解読、需要が語る 購買力は格差鮮明に 価格が実体を裏付け 結局は都心回帰 〝コロナ禍、新常識〟を追う 株高が演出する分譲マンション市況 住宅編
住宅供給は過剰になっている。人の寿命よりも建物の寿命が長い住宅も増え、土地を一生懸命に守ってきた考え方から土地を有効に活用する方法を模索する時代になった。都会のマンションにすべてを求めず、地方にもう(続く) -

三友、9月地価予測指数 三大都市の商業地 コロナ前水準なお遠く
住宅新報 10月5日号 お気に入り三友システムアプレイザル(東京都千代田区、堂免拓也社長)は9月27日、「三友地価予測指数(20年9月調査)」をまとめた。同社と提携する鑑定士162人を対象にアンケートを実施したところ、現在の商業地指数は、東京圏(続く) -

ムーディーズがリポート 中国恒大集団に警戒感 不動産市場は中長期で弱含み
住宅新報 10月5日号 お気に入り中国の不動産開発大手、恒大集団が世界をリセッション局面に向かわせるのではないかとの不安が広がっている。同社の社債利払いで債務不履行などが一部表面化し、資金難で住宅開発がストップして世界の投資家が警戒(続く) -

次期総選挙で強固な政権基盤カギ 日本の信用力 自民・岸田総裁の誕生で
住宅新報 10月5日号 お気に入り米格付け大手のムーディーズ・インベスターズ・サービスは9月29日、自民党総裁選の結果を受けて日本の信用力を評価するソブリン格付担当者がコメントを出した。 それによれば、シニア・ヴァイスプレジデントのク(続く) -

大型ビル供給は低水準 森トラスト調べ
住宅新報 10月5日号 お気に入り森トラストは9月27日、「東京23区の大規模オフィスビル供給量調査21」を発表した。それによると、大規模オフィスビル(延べ床面積1万m2以上)の供給量は23年(145万m2)、25年(134万m2)と比較的大きな供給が見込まれる(続く) -
ニュータウン再生で包括協定 多摩市 UR 〝次の50年〟に向けて
住宅新報 10月5日号 お気に入り東京都多摩市(阿部裕行市長)と都市再生機構(UR都市機構)は9月29日、多摩市域のニュータウン再生を推進するために、まちづくりに関する包括協定の調印式を市庁舎で開いた。多摩市ニュータウン再生方針、まちづくり(続く) -

明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第403回 住宅地の開放性と閉鎖性 門柱や街路樹など工夫し両立
【学生の目】 夏が終わり、外出しやすい季節になった。晴天の日に散歩をしていると、デザイン性と統一感があって目を引く不動産エリアがあった。電柱がなく、両側の歩道を加えた道路幅員が広く、空が大きく広が(続く) -
シリーズ・SDGs実現に挑む 県産木材でよりよい湘南へ 富士リアルティ・目標11ほか
宅建業を中心に、幅広い不動産事業を手掛ける富士リアルティ(神奈川県藤沢市、永松秀行社長)は、木造建築を通じて湘南地域の環境や街づくりへの貢献を図っている。8月には同社建築部門の「湘南乃工務店」が、同市(続く) -

ICT教育施設開設へ 横須賀市内で22年4月1日 テルウェル東日本など
住宅新報 10月5日号 お気に入りテルウェル東日本(東京都渋谷区)、東日本電信電話・神奈川事業部(NTT東日本、横浜市中区)、NTTe―Sports(東京都新宿区)は、横須賀市内に、次世代型ICT教育施設『スカピア』(仮称)を22年4月1日に開設する。横須賀市(続く) -

ネオキャリア スキャナ保存に対応 経費システム
ネオキャリア(東京都新宿区)は、同社で提供する人事向けクラウドサービス『jinjer経費』で、電子帳簿保存法の「スキャナ保全」に対応する新たな機能を9月16日に実装した。同法が求める「真実性の確保」や「可視性(続く) -

オーリック・システムズ・ジャパン ファイル管理システム 検索などで容易に
オーリック・システムズ・ジャパン(東京都港区)は、表計算ソフトなどのオフィス向けのファイルを取り込めて検索もできるクラウドサービス『Essentia AI』の先行利用ができるベータ版の提供を9月14日に始めた。(続く) -

富士通コミュニケーションサービス セミナー 従業員〝体験価値〟の向上を
人とICT技術の力によって、企業と顧客をつなぐ富士通コミュニケーションサービス(横浜市西区)は、EX(従業員)やCX(顧客)、DX(デジタル)の3つの「X」が意味する〝体験価値〟の観点から、従業員の声をビジネスの成長(続く) -

ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 185 小売電気とスマートメーター 日本不動産仲裁機構
2016年4月、一般家庭向けの電力の小売りが自由化されました。これによって戸建て住宅のみならず、集合住宅に住んでいる人も使用する電気を選べるようになりました。制度開始から5年が過ぎ、この仕組みも社会に定着(続く)