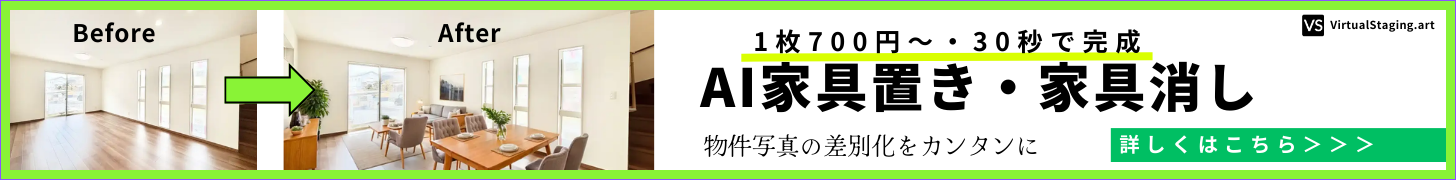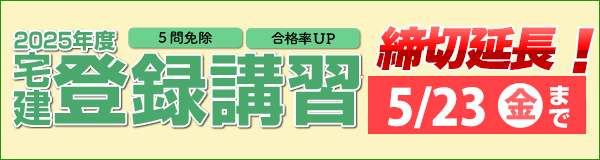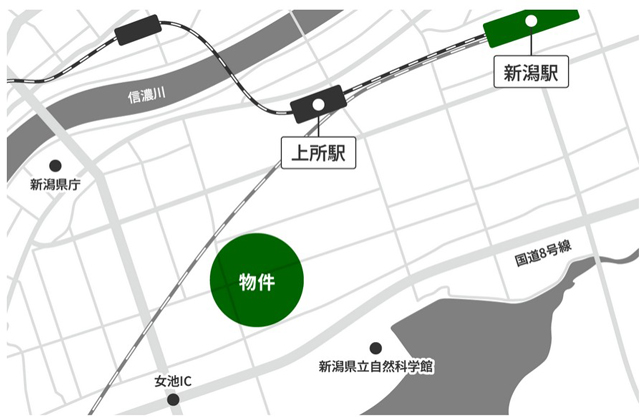政策
-

防火・避難関係規定を合理化 建基法施行令を改正 20年4月に施行
住宅新報 12月17日号 お気に入り政府は12月6日、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。建築技術に関する研究開発の進展や技術的知見の蓄積を踏まえ、同施行令のうち防火・避難関係規定を合理化するもの。同月11日に公布され(続く) -

〝東京一極集中〟解明へ 国交省が分析図る懇談会設置
住宅新報 12月17日号 お気に入り国土交通省は東京への〝一極集中〟の要因を多角的に分析・議論するため、「企業等の東京一極集中に関する懇談会」を設置し、12月6日に初会合を開いた。座長は元総務大臣の増田寛也東京大学大学院客員教授。 (続く) -

名古屋圏が全分野で続伸 全国総合は57カ月連続上昇 8月・不動産価格指数
住宅新報 12月17日号 お気に入り国土交通省はこのほど、8月の不動産価格指数(住宅)を公表した。10年平均を100とした全国住宅総合指数は112.9(前年同月比0.7%増)で、57カ月連続の前年同月比上昇となった。 住宅地は99.9(同3.0%減)、戸建て住(続く) -

19年度第2四半期リフォーム等調査 受注は12.8%増の3.25兆円 消費増税前の駆け込みか
住宅新報 12月17日号 お気に入り国土交通省は12月10日、19年度第2四半期(7~9月)受注分の「建築物リフォーム・リニューアル調査報告」をまとめ、公表した。08年から行われている調査で、18年度からは公表周期を半期ごとから四半期ごとに改めてい(続く) -

国交省 国土審土地政策分科会企画部会 「管理の確保」前面に 中間取りまとめ案で方針明記
住宅新報 12月17日号 お気に入り国土交通省は12月9日に国土審議会土地政策分科会企画部会(部会長=中井検裕東京工業大学環境・社会理工学院長)を開き、「新たな総合的土地政策」に向けた検討の中間取りまとめ案を公表した。 同案の表題は、「(続く) -

長期優良化推進事業申請受付を延長 国交省
住宅新報 12月17日号 お気に入り国土交通省は、当初12月20日までとしていた「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の交付申請の受付期間を20年1月31日まで延長すると発表した。同事業は、既存住宅の性能向上や良好なマンション管理につながるリフ(続く) -

ESGへの配慮を強化 TCFDコンソに入会 Re-Seed機構
住宅新報 12月17日号 お気に入り環境不動産普及促進機構(Re-Seed機構)はこのほどTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に賛同を表明し、12月10日に同提言に賛同する企業等で構成されるTCFDコンソーシアムに入会した。 同機構は、老(続く) -

改正地域再生法が成立 住宅団地再生へ向け規制緩和
住宅新報 12月10日号 お気に入り既存ストックの活用による〝多世代共生型〟の街づくりを促す「地域再生法の一部を改正する法律(改正地域再生法)」が12月2日、参議院本会議で可決、成立した。今年の通常国会に提出され、継続審議となっていた法案(続く) -

自民党税調小委 低未利用地特例 創設の方向か 不明地使用者課税も賛意多数
住宅新報 12月10日号 お気に入り自由民主党の税制調査会は12月2日と4日に小委員会を開き、20年度税制改正大綱の策定へ向け、個別の項目についての検討を進めた。 2日の小委員会では、全国宅地建物取引業協会連合会や全日本不動産協会が最重(続く) -

日政連全日議連 低廉物件流通の意義強調 国交省などへ税制改正要望
住宅新報 12月10日号 お気に入り全日本不動産政治連盟(日政連、原嶋和利会長)と全日本不動産政策推進議員連盟(全日議連、野田聖子会長)は12月3日と5日、合同で中央官庁と自民党を訪問し、20年度政策・税制改正の要望を行った。 3日には日政(続く) -

地域管理構想の指針を検討 国交省 国土管理専門委
住宅新報 12月10日号 お気に入り国土交通省は12月2日、第15回「国土管理専門委員会」(委員長・中出文平長岡技術科学大学副学長)を開いた。 同委員会では、将来的な土地の放置の増加を抑制するための「管理構想」を提唱している。国と都道府(続く) -

建築特性や買取再販に注目 国交省 住生活基本計画見直しへ初勉強会
住宅新報 12月10日号 お気に入り国土交通省は住生活基本計画の見直しへ向け、11月29日に社会資本整備審議会住宅宅地分科会の第1回勉強会を開いた。現行計画の達成状況を踏まえ、個別の論点を掘り下げる会合。今回は「ストック」をテーマに、現状(続く) -

共同住宅で活用進む 累計は1953件に 安心R住宅制度
住宅新報 12月10日号 お気に入り国土交通省は12月4日、18年4月に本格始動した安心R住宅制度(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)の19年4月から9月末までの制度実施状況を発表した。この数字は、広告に同制度の標章(ロゴマーク)が使用される(続く)