現地調査では目視する際に意識をしたい3点がある。
1点目は協定道路や埋められた井戸といった「見えないもの」、2点目は安全性を保てない擁壁や登記が必要な物置など「直すべきもの」、3点目は住宅の傾きや地盤沈下といった「専門家を入れるべきもの」、これら3点を意識して見ていきたい。
◎ ◎ ◎
現地調査では、(1)目視と(2)簡易計測の2つで行うのが基本だ。その(1)目視では漫然とではなく、この3点を意識しつつ万遍なく見ていくと、対象となる不動産がどういったもので顧客への説明や重要事項説明書の作成の際に何を注意すべきかよく分かってくるようになる。
1点目の「見えないもの」は当然、目視しても分からない。しかし、対象不動産の隅や周辺状況を見てみると他の不動産にない物が置いてある、見つかったりする場合がある。その場合は「何かある」ので注意をしていきたい。例えば前面道路が私道で公道との境目に侵入防止策、カラーコーンがあれば、利用制限のある協定道路の可能性がある。また、水道管が通っていなそうな場所に水栓柱があったり、敷地の隅に盛土があれば井戸がある、もしくは埋められた井戸があったりする。このように敷地の隅っこや周辺状況を見て「何でこんなのがあるのだろう」と思うものがあれば売主に確認するなど更に深堀りして調べていきたい。
2点目の「直すべきもの」は不動産の流通上、問題となるもの(阻害されるもの)なので建築基準法、ローン審査の目線で「これがあると問題になるな」と見ていく。違法性を疑われるもの、登記情報と異なるもの、不動産として扱えないものが該当する。例えば二段擁壁など安全性が低い擁壁は再建築の際に特定行政庁からつくり直しが条件となることがある。登記されていない物置はローンを受けるまでに撤去か置いておくなら表示登記が必要になる。専門家を入れずとも気づいてチェックしていきたい。
3点目の「専門家を入れるべきもの」とは、宅建業者としては判断できずとも専門家なら判断できることで、買主が想定していないことが起き売買でトラブルとなりそうな状態のことだ。例えば住宅の傾きや地盤沈下など住むのに際して安全性に問題がありそうな場合や、建物等に未登記部分がありそうな場合などだ。他に大きな越境や境界が分からない場合も該当する。 対象不動産の安全性、売買範囲などで現地で「あれっ」と思ったら専門家を入れて明確にしていくか、売主・買主に専門家の利用をアドバイスしていこう。
宅建業者は最低限、専門家利用のアドバイスをしておけば何かあっても取引責任は小さくなる。リスクヘッジはしっかりしておきたい。
◇ ◆ ◇
【プロフィール】
はたなか・おさむ=不動産コンサルタント/武蔵野不動産相談室(株)代表取締役。2008年より相続や債務に絡んだ不動産コンサルタントとして活動している。全宅連のキャリアパーソン講座、神奈川宅建ビジネススクール、宅建登録実務講習の講師などを務めた。著書には約8万部のロングセラーとなった『不動産の基本を学ぶ』(かんき出版)、『家を売る人買う人の手続きが分かる本』(同)、『不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)など7冊。テキストは『全宅連キャリアパーソン講座テキスト』(建築資料研究社)など。
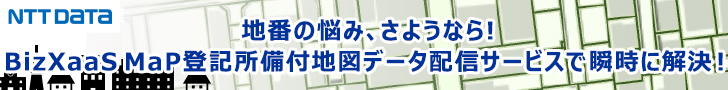

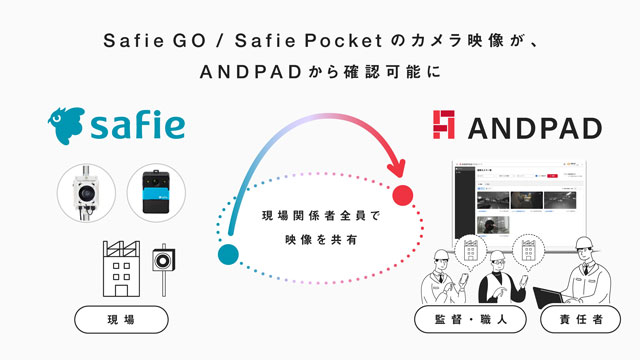




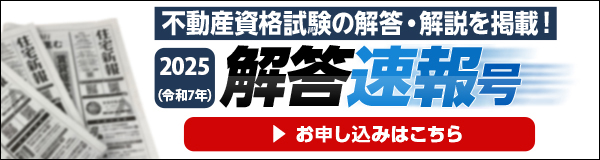

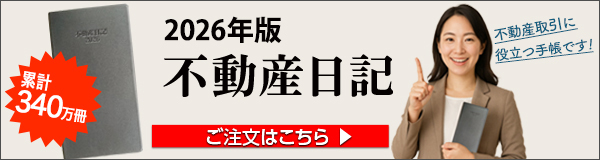
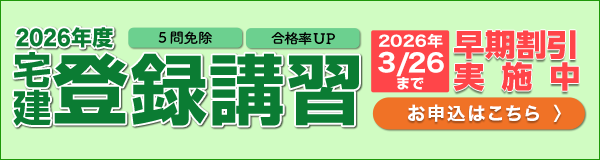





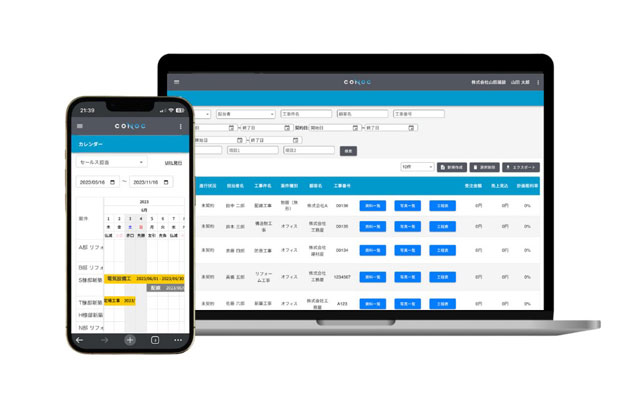


.jpg)
.jpg)

