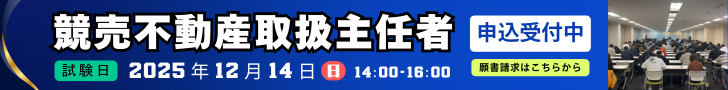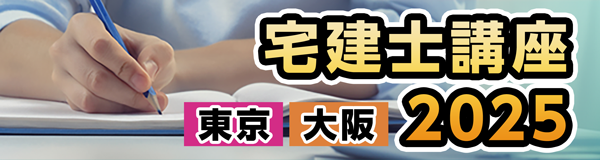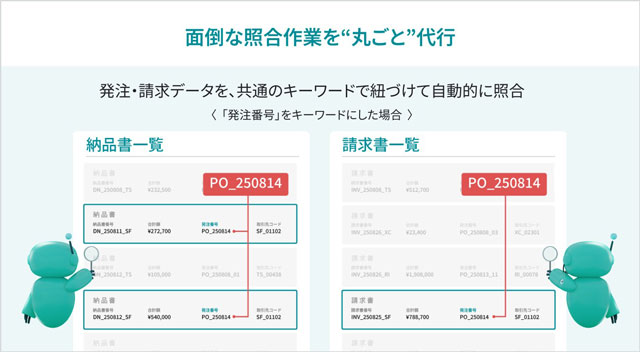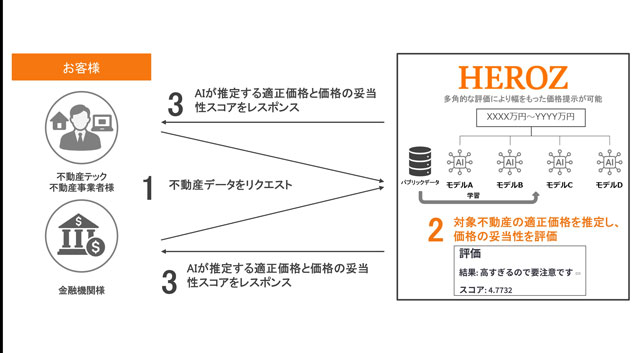フリーアドレスやフレキシブルなどオフィスの多様化が進んでいる。オフィスだから仕事の効率性が最優先だが、そのためにも「居心地の良さ」(快適性)は外せない。むしろ居心地の良さが仕事の効率化をもたらしているというべきだろう。人工知能(AI)は電力さえあれば24時間疲れを知らず働くが人間はそうはいかない。
◇ ◇
では、居心地とはなんだろうか。それは自分がある場所や地位にいるときの気持ちだが、ここでは〝場所〟に限定しよう。人間にとっての主な場所は住まい、職場、住んでいる街である。しかし、これまで居心地が重視されてきたのは住まいぐらいで、職場は近年ようやくその重要性が認識され始めたところだろう。次なるテーマは「街の居心地」である。
福岡市が市民に毎年行っているアンケート調査によると、市民の99%が「この街が好き」と答えている(23年度市政に関する意識調査)。これはまさに驚異的な数字で、おそらく全国の政令指定都市の中でも奇跡的数字ではないだろうか。この点について、福岡テンジン大学学長の岩永真一氏はこう語る。
「毎年90%台後半の高い数字になっていたものの今回の99%という数字は通常あり得ない数値だ。要因としては、定評ある住みやすさに加えて、福岡市が〝比較されやすい都市〟だからだと考える。福岡市は人口の流動性が高く、他の都市や土地から移り住んできた人たちが多く、彼らにとっては以前住んでいた都市や土地との比較が容易であり、結果的に〝福岡好き〟になる傾向がみられる」(メルマガ「フクリパ」近藤益弘氏記事より)
学術的に分析すればその通りだと思うが、出張や観光などでたまにしか訪れない者にとっても、「街を歩いていて楽しい」と感じるのは筆者だけではないと思う。従来からの定評ある住みやすさとは「都会なのに自然が豊かで、都市機能が都心にコンパクトにまとまっていて便利。更に食もおいしく、物価も意外と安くて何でも一通りそろっている」(岩永氏)ということだが、福岡市が魅力ある街になっているもう一つの大きな要因は〝市長〟にあると思う。
現在の高島宗一郎市長は2010年に史上最年少の36歳で初当選し、現在は4期目だ。最初にやった大仕事が航空法によって制限されていたビルの高さ制限を関係当局に掛け合い、福岡市役所の屋上にある避雷針の高さまで引き上げさせたことだ。これが現在進行中の再開発〝天神ビッグバン〟によるビルの建て替えラッシュにつながっている。
街に活力を取り戻したいという変革精神をもった市長がいる街は、歩いていてもその志が伝わってくるようで気持ち(居心地)がいいのである。
◇ ◇
コロナ禍では働き方改革が叫ばれ、リモートワークが定着し、いずれは〝通勤のない日〟の到来も予想された。しかし、コロナの収束と共にリモートワークも下火となり、今は〝居心地の良い〟オフィスが用意され、再び社員の多くが呼び戻されることになった。日本人にとっては一人で仕事をするよりも社員同士が顔を合わせ雑談(懇談?)しながらのほうが性に合っているのだろう。
では、コロナ禍でもう一つ叫ばれた「住まい方改革」は、その後どうなっただろうか。今でも残っている影響といえば、やはりリフォームやリノベーションに対する関心の高まりではないか。つまり〝おうち時間〟の快適化ニーズがコロナを機に各段に高まったことは確かだ。
このように住まい、職場、街へと拡大しつつある「場所の快適性」に対する探求心の背景にあるのはなんだろう。それはおそらく、仮に全ての居場所が快適になったとしても、なお心は満たされないままという予感であり、恐れである。ではそれはなぜかと聞かれても、答えは深い霧に隠れたまま歴然としない。