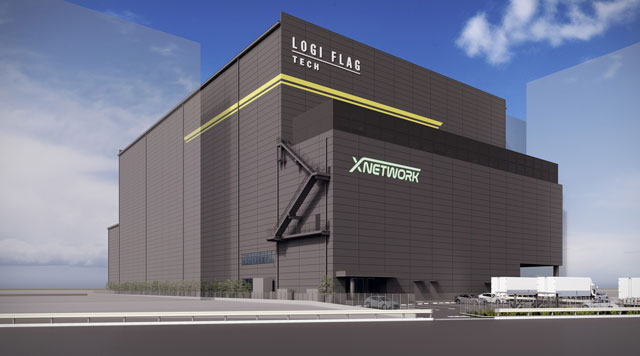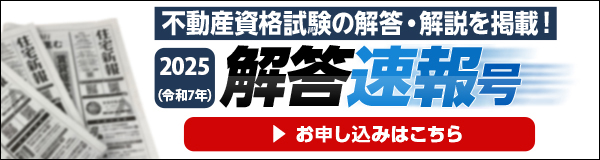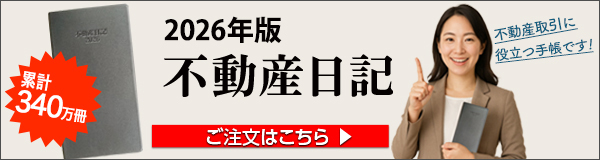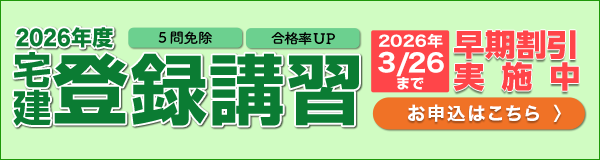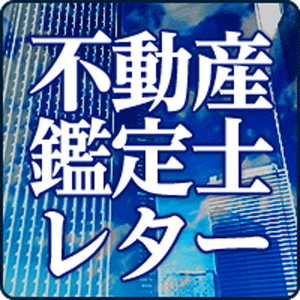今回は教える側の視点。新人が法令上の調査において何が一番分かりづらいのか。
おそらく「建築基準法」と「その取り扱い」ではないだろうか。春先にいくつか新人への研修や講演の機会をいただいた。法令上の調査でこの建築基準法の話になると、場の空気感が「?」となることが多かった。
◎ ◎ ◎
筆者の説明が下手なせいでもあるが、新人にベースとなる建築基準法の基礎知識がなく、筆者と「これを知っているよね」という共通認識がなかったからだろう。宅建士を取得済もしくは一定程度勉強をした方は基礎知識があるのでそこまではなかったが、それ以外の方には段階を追って説明しないといけなかった。
「何が分からないのか」、「どの点が分かりづらいのか」を直接聞いてみたところ、次の3点にまとめられた。
1点目は「建築基準法を調査する目的」、2点目は「調査をすべき条文」、3点目は「言葉(専門用語)の定義」この3点だ。
なお、2点目と3点目は宅建士取得済等の方は大丈夫。ただ、それ以外の方は丁寧な説明が必要と言えた。建築基準法に触れるのが始めてなので、この3点が頭にスッと入らないのも当然だろう。
1点目の調査目的は、建築基準法だけではなく都市計画法など他の法令も一緒。なぜその法令を調査するのか目的が見えず今ひとつピンとこないとのことだった。
「不動産の利用や建物を建てることは様々な法令で制限が掛かるので、売買当事者に対して意図する利用や建築ができるかどうか、説明するために調査する」
このような言い方が調査目的として妥当だろうか。なお、建築基準法ではまず建築ができるかの可否があり、その上で建物の面積、形状など制限がかかるので、それを判断し説明するために調査すると言える。
◎ ◎ ◎
2点目は調査すべき条文。「幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル接道する」だけでは分かりづらいので、主に42条の道路の定義、43条の敷地等と道路の関係、この2つの条文から説明した方が良い。他にも建築基準法の第三章を説明すると、用途地域などの調査もなぜ必要か分かりやすいだろう。
◎ ◎ ◎
3点目の言葉の定義は不可欠で、専門用語は1つ1つ紐(ひも)ほどいて説明する。建築主事は建築基準法を取り扱う公務員であり、その建築主事がいる役場が特定行政庁。特定行政庁である市区町村役場で建築基準法の確認ができる、という順である。
教える側は研修等の時間の都合もあるので「これぐらいは分かっているだろう」から始めがちだ。良い反省になった機会であった。
◇ ◆ ◇
【プロフィール】
はたなか・おさむ=不動産コンサルタント/武蔵野不動産相談室(株)代表取締役。
2008年より相続や債務に絡んだ不動産コンサルタントとして活動している。全宅連のキャリアパーソン講座、神奈川宅建ビジネススクール、宅建登録実務講習の講師などを務めた。著書には約8万部のロングセラーとなった『不動産の基本を学ぶ』(かんき出版)、『家を売る人買う人の手続きが分かる本』(同)、『不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)など7冊。テキストは『全宅連キャリアパーソン講座テキスト』(建築資料研究社)など。