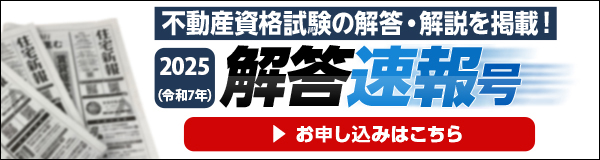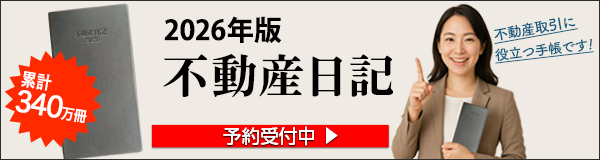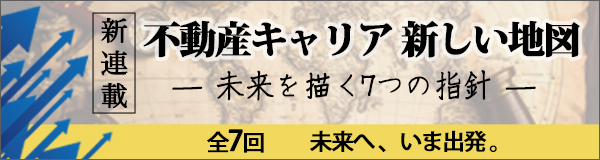不動産取引現場での意外な誤解 記事一覧
-
不動産現場での意外な誤解 売買編161 共有の相続物件が勝手に用途変更されたら?
Q 当社は、共有の不動産を売買したり賃貸したりすることがありますが、あまりトラブルになったことはありません。それは、当社の社員が、共有の物件については常に「全員の合意」という原則を守っているからだと(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編160 賃貸借で違約金の他に損害賠償請求ができる?
Q 建物賃貸借契約を締結する場合、通常、借主が契約違反をしたときは契約の解除と共に損害賠償の請求ができる旨を定めることが多いと思いますが、どうなのでしょうか。 A 居住用の場合は明文化したものはあま(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編159 古い建物の修繕義務に関する具体的な目安は?
Q 前回、建物賃貸借契約においては、借主が建物の古いのを承知の上で契約したとしても、貸主が修繕義務を負うと書いてありました。 A その通りです。しかし、だからと言って、すべての建物について貸主が修繕(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編157 更新ごとに更新料と敷金の償却が取れるか?
Q 前回、保証金の「償却」と「敷引き」は同じものだという話がありましたが、これは一般に、「償却」は商業系で使われ、「敷引き」は住居系で使われるということでしょうか。 A 必ずしもそういうことではあり(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編156 借主が差し入れる敷金と保証金は同じものか?
Q テナントビルの場合には、敷金の代わりに「保証金」という名目で金銭を預かるケースがあります。これも民法622条の2でいう「敷金」になるのでしょうか。 A この保証金が、借主の貸主に対する債務の担保とし(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編155 敷金の返還を後払・年払にすることもできる?
Q 敷金について、民法改正によってその定義と共に、返還時期についても明確になりましたが(民法622条の2)、一説によりますと、その返還債務と借主の建物の明渡し債務とは同時履行の関係に立たないと言われていま(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編154 共益費は実額よりも多く請求できる?
Q 前回、共益費も借地借家法の適用があるということでしたが、たとえば、共用の電気料金や水道料金を実際の額よりも多く請求することはできるのでしょうか。 A できます。しかし、程度によります。例えば、貸(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編153 共益費も借地借家法の適用があるか?
Q 建物賃貸借契約においては、「共益費」という名目で賃料以外の費用を支払うことがありますが、この費用についても、賃料の場合と同じように借地借家法における増減請求権の規定(32条)が適用されるのでしょうか(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編152 賃料改定特約の有効性はどのように判断する?
Q 前回のマスターリース契約における賃料増額条項と同じような事案で、大型スーパーストアのいわゆるオーダーメイド契約における賃料増額改定条項の有効性が争われた裁判がありましたが、こちらの方の結論はどう(続く) -
不動産現場での意外な誤解 賃貸借編151 新規募集で賃料を安くしたら値上げは容易か?
Q 当社は、賃貸管理業者を兼ねているため、オーナーのためにも安定した賃貸経営を目指しています。そのため、物件によっては、入居者の新規募集に際し、賃料を安くして早く満室にし、次の契約更新時に更新料を免(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編160 共有者の1人が勝手に共有物を賃貸したら?
Q 前回話に出た、他人物売買による所有権の移転がうまくいかなかったらどうなるのでしょうか。 A その前回の判例と同じような事例として、多数持分権者が少数持分権者の同意を得ないで勝手に共有地を売却し、(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編159 共有者の1人が勝手に共有物を売却したら?
Q 一般に、共有物を賃貸する行為は「管理行為」になるが(民法252条)、それは民法上の賃貸借のような場合の話であって、借地借家法の適用を受けるような賃貸借の場合には、それは「法律的な処分行為」として共有物(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編158 移記閉鎖登記簿にはどのようなものがあるか? 登記のコンピュータ化や粗悪用紙、枚数過多による移記閉鎖登記簿があります
Q 前回は、不動産の閉鎖登記簿としての「移記閉鎖登記簿」の話が出ましたが、それは主にコンピュータ化が進められたことによるものということですか。 A そればかりではありませんが、コンピュータ化に伴うも(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編157 担保権の名義人役員が全員死亡していたら?
Q 前回は、抵当権者である会社の所在が不明の場合に抵当権の登記が抹消できるかという話でしたが、その事例は、不動産登記法でいう会社の「行方不明」とは異なるものでした。 A その通りです。不動産登記法で(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編156 抵当権者(法人)の所在が不明でも仲介できる?
Q 以前のこのコーナーに、所有者不明土地に関連し、その土地に登記されたままになっている、いわゆる「休眠担保権」の抹消手続の問題が取り上げられていましたが。 A それは、〔売買編〕の第124回の内容だと思(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編155 「相続土地国庫帰属法」の目的と内容は?
Q 所有者不明土地に関し、土地の所有権を放棄できる「相続土地国庫帰属法」について伺います。 A この法律の目的は、前回にも申し上げた通り、所有者不明土地の「発生予防」であり、「相続等により取得した土(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編154 不明土地に関する不動産登記法の改正内容は?
Q 今回は、所有者不明土地に関する不動産登記法の改正部分を聞きます。 A 不動産登記法の改正で最も重要な改正は、「相続登記」を義務化したことです(不登法76条の2)。これにより、今後の所有者不明土地の発生(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編153 民法の共有規定の改正で最も重要な改正は?
Q 所有者不明土地に関する民法の改正内容については、相隣関係以外の共有の規定でかなり重要な改正がなされたと聞いていますが。 A その通りです。共有の規定については、まず最初に、共有物の「使用」に内す(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編152 所有者不明土地に関する民法の改正内容は?
Q 所有者不明土地に関して具体的に伺いたいと思います。まず、民法の改正内容です。 A 民法については、専ら「利用の円滑化」という観点からの改正が中心で、具体的には、主として現行の相隣関係の規定(209条(続く) -
不動産現場での意外な誤解 売買編151 所有者不明土地に関する民事法制の見直しとは?
Q 所有者不明土地については、すでに特措法が成立し、対策がとられているようですが、それらの対策を更に進めるための民事法制の見直しに関する法律が先の通常国会で成立したと聞きました。その内容について知り(続く)