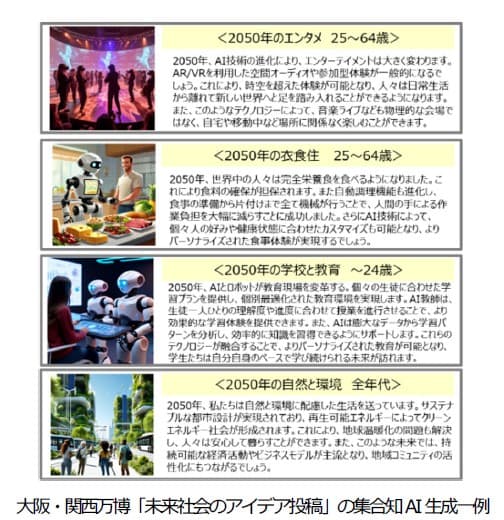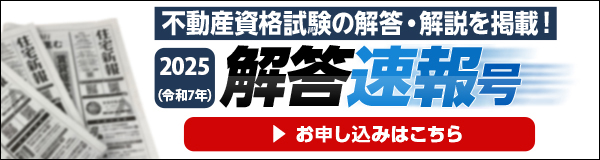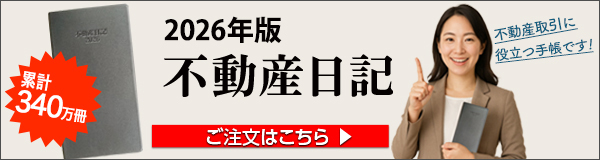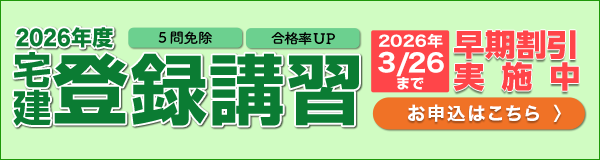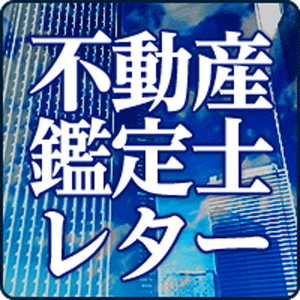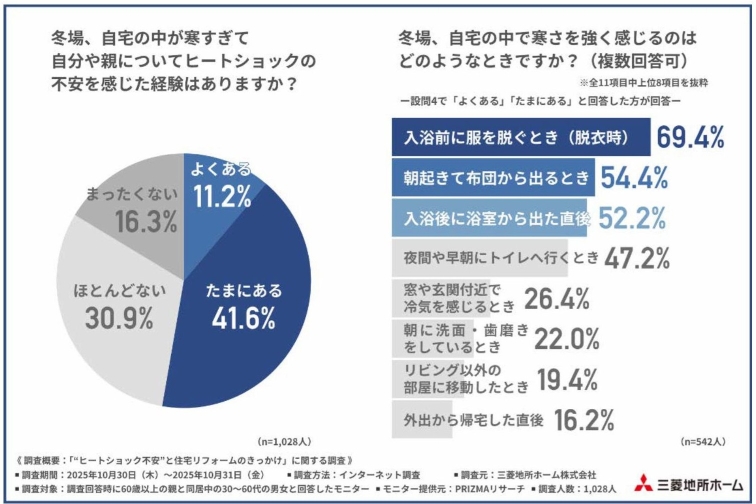対象不動産の調査を深めるために、隣地や近隣の建築計画概要書(以下、概要書とする)を取得し、対象不動産と隣地や近隣がどのような関係にあるのか確認をした方が良い場合がある。ケースに応じて対応していこう。
大きくは次の2つのケース。(1)対象不動産とその前面道路との関係がよく分からない場合、(2)隣地との境界とその状況、擁壁等の扱いがよく分からない場合だ。
概要書で分かるのは建築基準法における敷地と前面道路との関係、建物概要、建物と土地の面積や規模構造、敷地形状と建物配置、寸法、方位、建築主等といった関係者の情報などだ。
これらの情報のうち隣地や近隣の概要書で確認したいのが、建築基準法に関する情報と敷地形状と寸法の情報だ。
(1)対象不動産とその前面道路との関係がよく分からない場合とは、主に道路中心線の位置とセットバック範囲、前面道路の建築基準法上の扱いなどだろう。たとえば前面道路が2項道路なら隣地や道路向かいの敷地の概要書を確認することで、どの程度のセットバックが必要か確認が取れる。記載されている道路中心線を対象不動産に当てはめることでセットバック距離や面積を推測できるからだ。特に築年数が浅い建物の概要書の取得は有効で、記載された道路中心線は最近決められており信頼性が高い。また、対象不動産が奥まった敷地で複数の不動産と共有で前面道路を利用しているなら、建築基準法の観点で前面道路がどのような利用を想定して建築が許可されているかを確認する。各不動産が幅員2メートルずつ道路に接しているとかである。
(2)隣地との境界に塀がある場合で、境界標がないため共有塀なのかどちらかの所有かよく分からない場合がある。その際も隣地等の概要書を取得し塀の記載があれば共有塀かどちらかの塀か判別できることがある。他にも隣地との境界が不明なとき、概要書記載の敷地形状や寸法を見て現地で確認すれば「おそらくこの辺りの線が境界でないか」と当たりをつけることができる。また、対象不動産と接している擁壁の安全性の確認も概要書で推測が付けられる。先日も隣地の擁壁が気になり概要書を取得したら「開発行為時に設けた擁壁」ということが分かった。建築指導課からは再建築時の判断としながらも「安全性が担保されていそう」という判断をもらえた。確定測量図や地積測量図等の書類があれば境界等の確認は簡単だが、そうでない場合は隣地や近隣の概要書はとても参考になると言えるだろう。
特定行政庁によっては概要書の取得が1物件1000円以上のところもあり、その場合はコスパから取得は要検討と言えるが、数百円程度なら積極的に取得して活用しても良いかもしれない。
◇ ◆ ◇
【プロフィール】
はたなか・おさむ不動産コンサルタント/武蔵野不動産相談室(株)代表取締役。2008年より相続や債務に絡んだ不動産コンサルタントとして活動している。全宅連のキャリアパーソン講座、神奈川宅建ビジネススクール、宅建登録実務講習の講師などを務めた。著書には約8万部のロングセラーとなった『不動産の基本を学ぶ』(かんき出版)、『家を売る人買う人の手続きが分かる本』(同)、『不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)など7冊。テキストは『全宅連キャリアパーソン講座テキスト』(建築資料研究社)など。