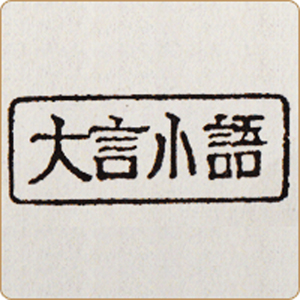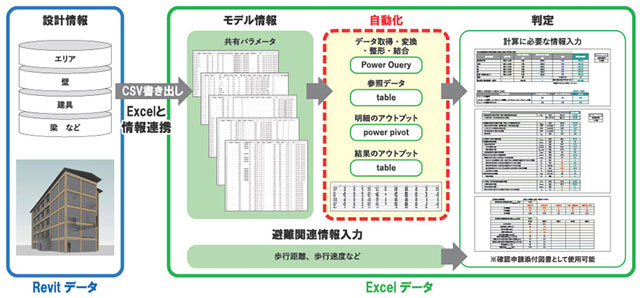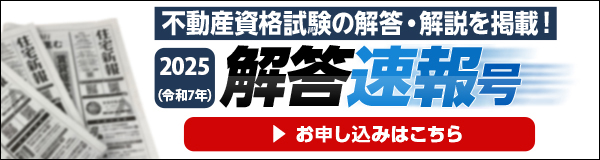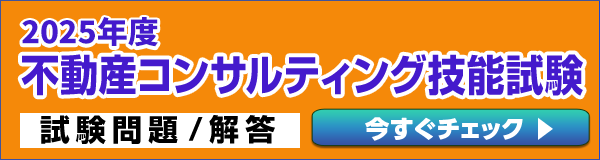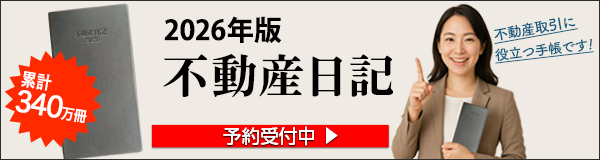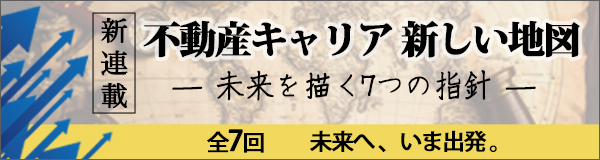今年は「昭和100年」に当たるが、直近の100年では、気象災害の激甚化・頻発化が目に見える形で進んだという。特に近年は、災害が他人事でも非日常でもなくなったと実感せざるを得ない機会が増えた。そんな時代の流れに伴い、防災の常識もまた、変化している。
▼例えば、ここ数年で耳にするようになったのは、「ローリングストック」や「フェーズフリー」といった言葉だ。前者は、「日常備蓄」とも言われ、「日常消費する食品を少し多めに買い置きし、消費した分を買い足すことで、常に一定量の食料を備蓄する」といった備蓄食料を保つ方法を指す。後者は「平時に利用しているものやサービスを災害時にも役立てられるようにデザインする」といった防災に対する考え方だ。いずれの言葉からも、防災とは日常の延長線上であり、〝万が一に備える〟ことではなくなった現況が垣間見える。
▼住宅供給事業者が災害に強い住宅を訴求する中、回復力や復元力を指す「レジリエンス」という言葉が浸透しつつある。パナソニックホームズの「暮らしの防災対策に関する意識調査」によれば、災害発生時も避難所ではなく、自宅にとどまりたいとの回答が過半を占めた一方、「在宅避難」の言葉や意味を「知らない」との回答は約7割に上るという。
▼認知率は防災対策の実施状況によって大きく変わるようだが、数字の背景には、様々な業界課題がありそうだ。