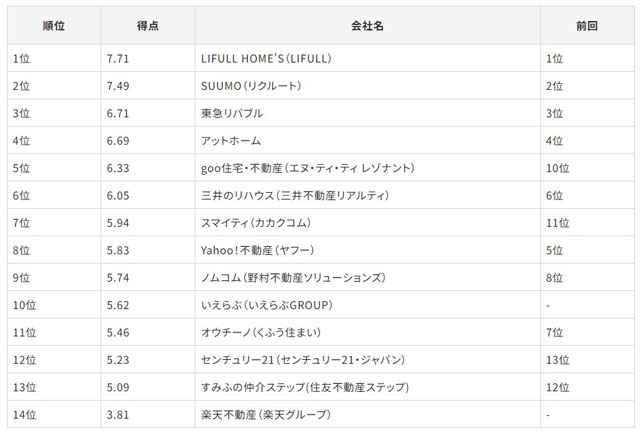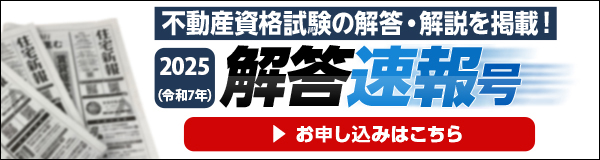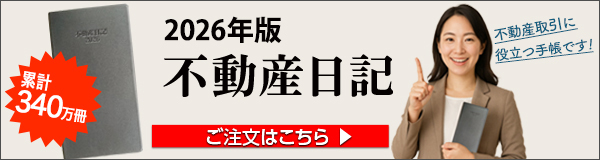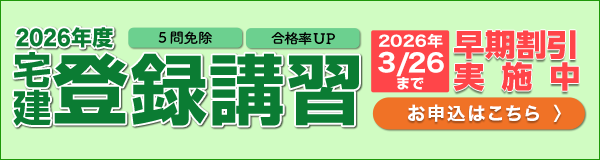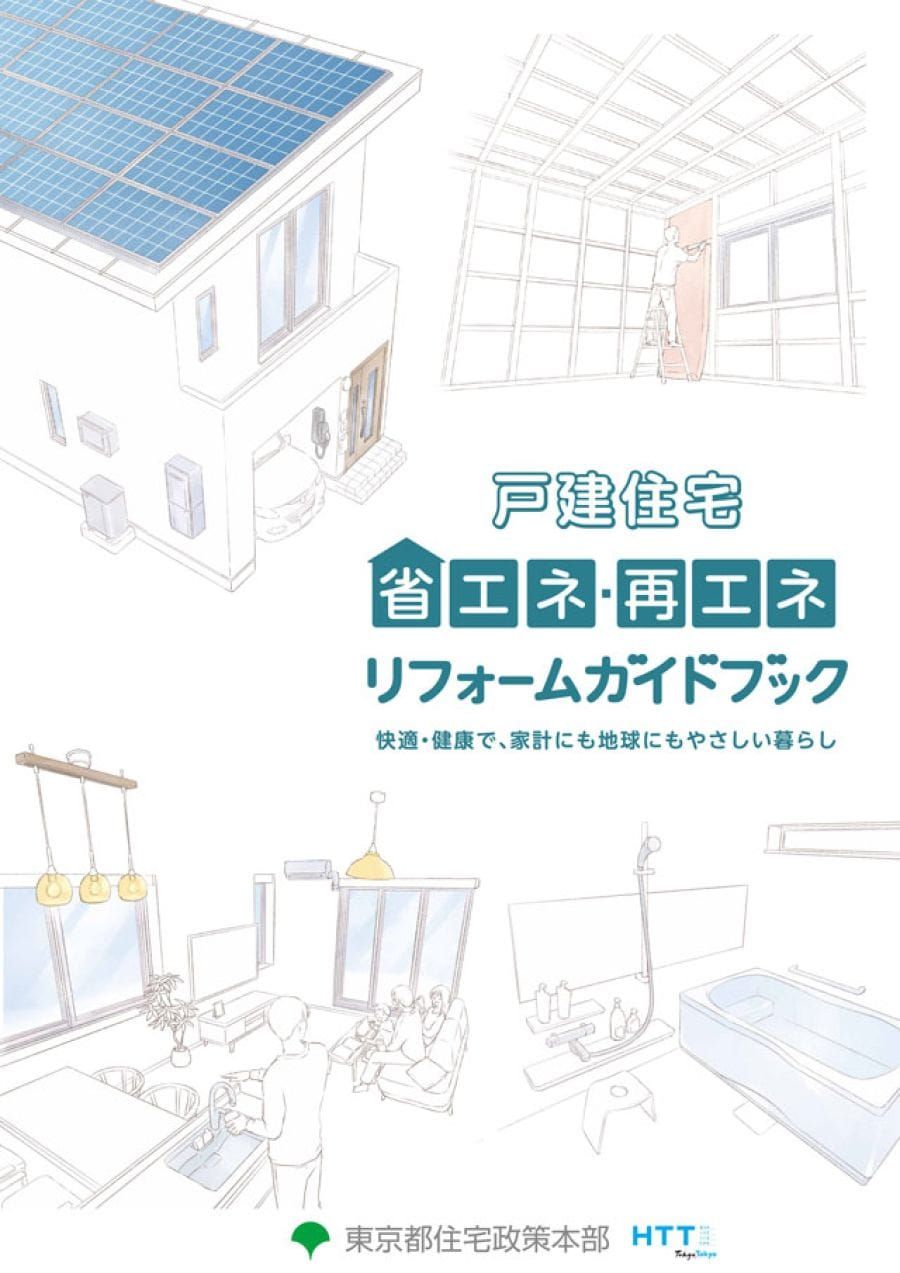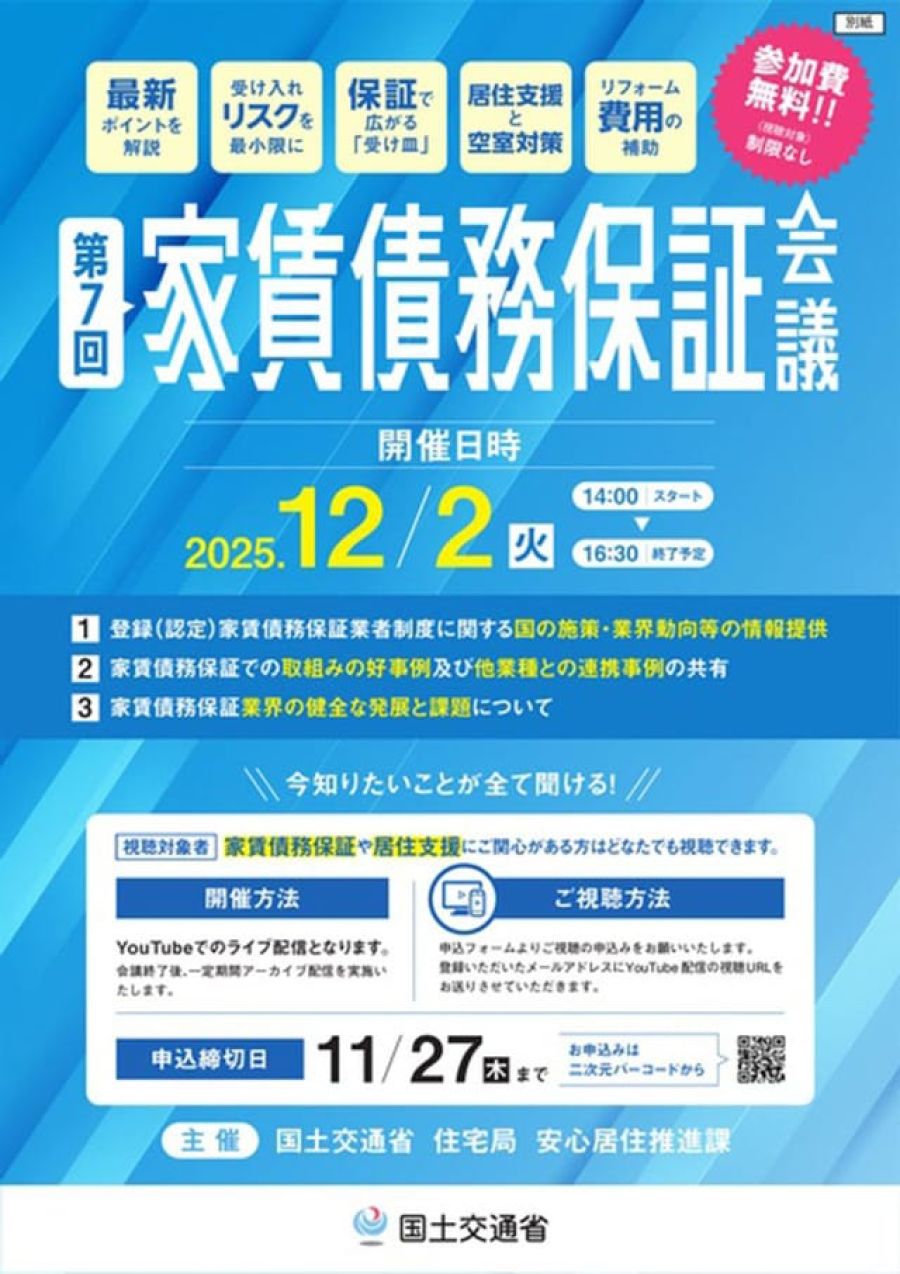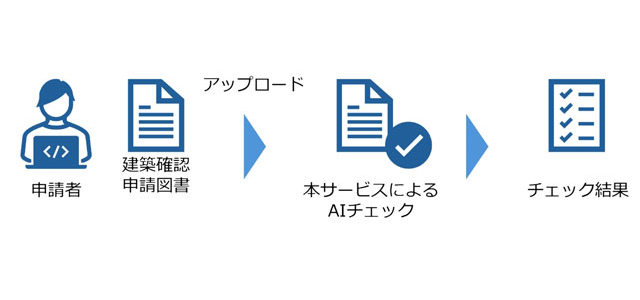企業経営にとって、従来からの「仕事と子育ての両立支援」に加え、今後は「介護との両立問題」が重いテーマとなってくる。経済産業省によると、家族の介護をしながら仕事をする人(ビジネスケアラー)が2030年には318万人に達し、介護に起因した労働総量の減少と生産性の低下による経済損失額が9兆円以上にも達するという。それでなくても人手不足が深刻化する中、今後はいかに介護負担による社員のパフォーマンス低下を防ぎ、介護離職を防ぐかという課題が企業にとっての最重要課題となる可能性が高い。
そのため経産省は昨年3月、「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表。更に厚生労働省は今年4月から「改正育児・介護休業法」を施行し、企業に介護離職防止のための「雇用環境整備措置」を義務付けるなど、政府も「仕事と介護の両立支援」に本腰を入れ始めたようだ。
不動産業界でも大手を中心に取り組みが進み、例えば従来から、休業法で定めている以上の介護休業日数を社内的に設定したり、最近では人事部での相談体制を強化、社員がワンストップで必要な情報が得られるガイドブックを作成するなど情報提供に努めている。情報提供やガイドブックブック作成は中小でも可能であり、できれば大手で効果を発揮しているフレックスタイムの導入も検討すべきだろう。エンドユーザー相手の販売や仲介業務は大手も中小も「人間力」が決め手といわれてきた。更に昨今はIT人材の確保も欠かせない。しかし、近年は高いスキルを持つ人材ほど流動化が激しくなっている。中途採用にも力を入れざるを得ない。そこで、社員の介護問題に力を入れている企業であるというカラーを打ち出すことができれば、中途採用においても強みを発揮するのではないか。
経産省は「経営者向けガイドライン」の中で、全企業が取り組むべき最も重要な課題は「経営層のコミットメント」だと指摘する。経営者自身が介護問題を理解し、「仕事と介護の両立が困難になることで会社にどういったリスクが生じるのか、また逆に仕事と介護の両立が達成されることによって どういったリターンが会社に生じるのかを整理しておく必要がある」という。この点は特に中小不動産会社の経営者の自覚を促したい。
今後、ビジネスケアラーの増大は避けられない。不動産業界では経験を積んだ40代、50代の管理職クラスの転職も多くなってくるだろう。優秀な人材の離脱を食い止めるためにも、介護問題への対応は欠かせない。
共働き世帯が一般化している今、働く誰もがいずれは「家族の介護」という問題と向き合うことになる。長寿化と少子化が加速していることも踏まえると、介護問題への対応を誤れば、日本は将来的にその経済力を大きく損う危機に直面していることを肝に銘じるべきだ。