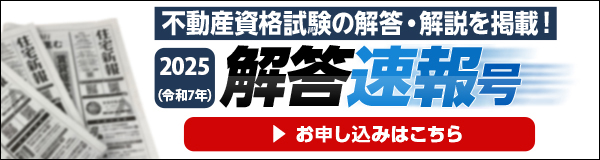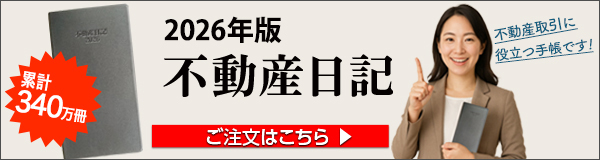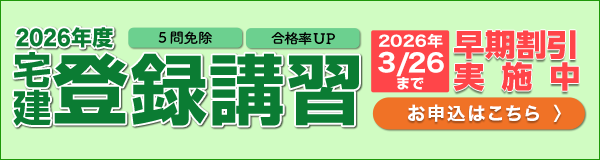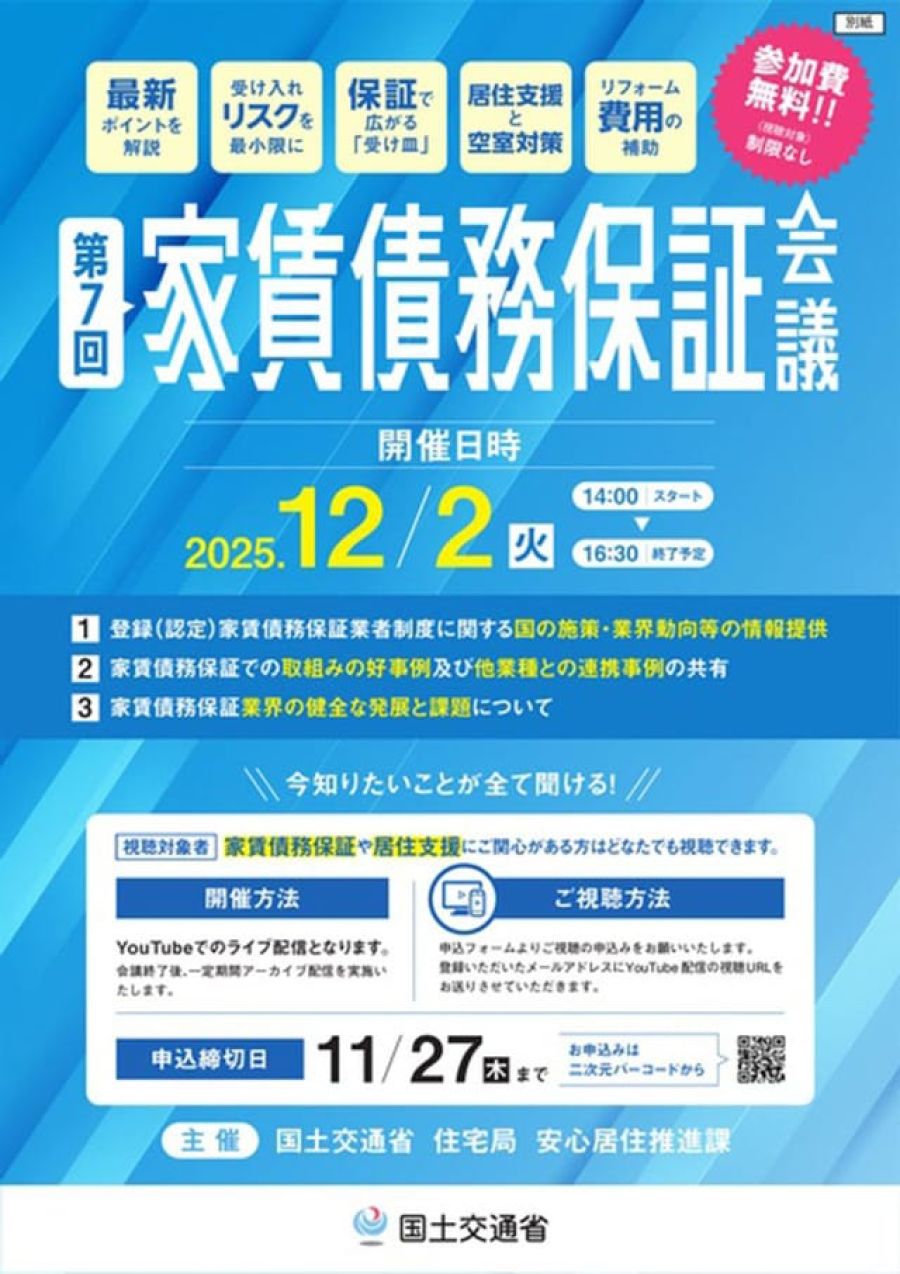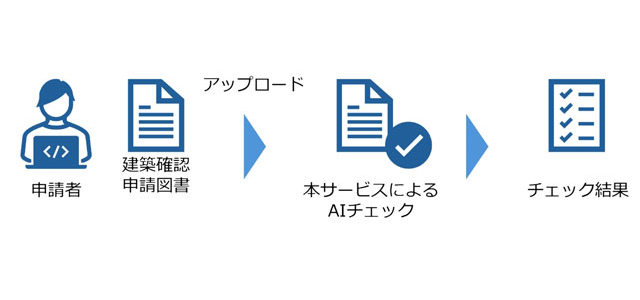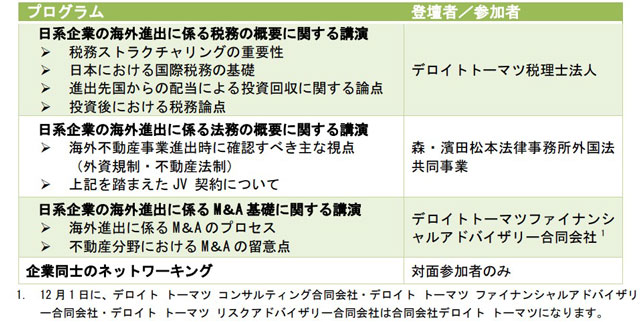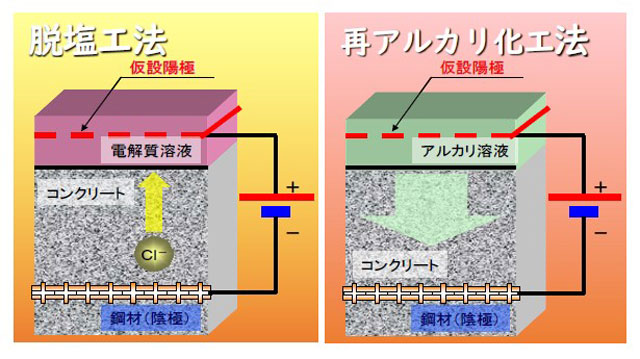首都圏を中心に近年、定期借地権を活用した分譲マンションの供給が目立ち始めた。不動産経済研究所によると今年は首都圏で2000戸に達する見通しで、ここ数年と比べると約2倍の規模となる。その背景の一つが「地代前払い方式」の魅力が地主層の間に浸透し始めたことだ。
同方式は借地契約期間中の地代の全額もしくは一部を地主に前払いするものだが、全額を一度に払う〝一括〟前払い方式も大手ディベロッパーの間では多用されている。借地期間を70~75年程度に設定した場合、地主は土地を売らなくても土地価格の70~75%程度の資金を得ることができる。このあまりに大きな魅力が返って仇となり、当初は地主から信用されない時期もあったようだ。しかし東京・豊島区や渋谷区の庁舎建て替え、格式ある神社の本殿再建などでこの方式が採用され始めると、その情報が一等地に土地を持つ一般地主層の間で知れ渡り、徐々に活用が始まったということだ。
焦点は今後の動向だが、定借マンションがこれからも増えていくためには借地人(ユーザー)側のメリットを明確にすることだ。一括前払い方式における地主側のメリットは既に述べたように十分にある。受け取った前払い地代は契約年数で割って毎年均等にその年の収入として計上できるという税務上のメリットまで付いている。
ディベロッパーにとっても、都心の駅前や高級住宅街でマンション事業ができるメリットは大きい。地代を一括前払いしてもその分は分譲価格に含まれているので販売時に回収することができる。一等地だけに売れ行きに心配はない。残るはマンション購入者側のメリットだ。購入者にも大きなメリットがあれば〝三方良し〟で、普及条件がそろう。
購入者側の第一のメリットは所有権マンション価格と比べた割安感だろう。土地価格の70~75%が地代とすると、本来なら25~30%の割安感があってもよさそうだが実際はそうならない。なぜなら地代交渉の中で固定資産税相当分が入り込むケースがあったり、解体準備積立金などの負担もかかったりするため、実質的には10~15%程度の割安感にとどまっている。これで借地期間終了時に建物を解体して更地返還する責務(デメリット)とのバランスがとれるかどうかがポイントとなる。前払い地代をいくらに設定するかはディベロッパーと地主との交渉力次第なので、割安感を更に増やせるような交渉力に期待したい。
期間終了時の更地返還が法律で決まっていることをデメリットと見るかどうかの議論も必要だ。所有権マンションのように老朽化したときに大規模修繕か建て替えかなどをめぐって区分所有者間でもめる可能性が低いからだ。この点は事業者側も定借の魅力として明示すべきだろう。更にマンションにおける土地所有とは何かという根本的議論も期待する。