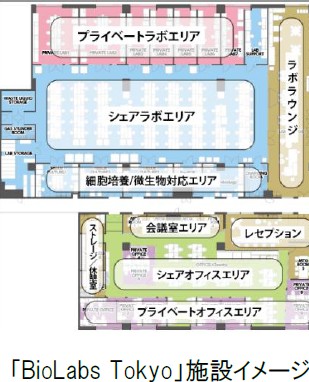新型コロナウイルス感染拡大により在宅勤務が増えたことで〝オフィス不要論〟が台頭し、オフィスの在り方が議論されるようになった。東京のオフィス需要はコロナ前の水準に戻せるのか。それともコロナ禍で存在感が増したサテライト型やシェアリング型といったフレキシブルオフィスが企業に定着することで新たな需要を掘り起こせるのか。市場の読み方が難しくなっている。
オフィス仲介大手の三鬼商事によれば、東京都心5区の直近9月末時点の平均空室率は6.43%と19カ月連続で悪化した。賃料は前月32カ月ぶりに2万1000円台を下回ったがなお下落が止まらない。ザイマックス不動産総合研究所では、「東京23区は4~6月の空室率が2.96%と5四半期連続で上昇した。解約予告を含めた募集面積率は5.75%と空室率との差が広がり、予告から退去までの6カ月間に次のテナントが決まらないケースが増えた」とする。テレワークを受けて借りていた床を返すオフィス集約の動きに注目が集まり、富士通や日立製作所など大手が賃貸面積を大幅に減らすニュースが駆け巡ったことで将来の未利用空間もあぶり出した。在宅勤務は働き方の多様性の利点とコミュニケーション不足も浮き彫りにした。
ワクチン接種が急速に進んだことで出社体制へ徐々に緩和する動きがあるものの、在宅勤務と出社のハイブリッド勤務が定着する見方が大勢だ。本社・支社はリモート会議用の個室やブースを増やしたり、座席を決めないフリーアドレスに対応するレイアウト導入などがテナントから重視されるのは明らかだ。
一方、フレキシブルオフィス市場は拡大しそうだが、多様な働き方はワーカーが企業を選ぶポイントになる可能性をはらんでおり、優秀な人材獲得の面からも手が抜けない事業領域として見込まれる。
新型コロナ前の出社体制がなくなれば従来の業務スペースは必要としない。
「単純に1人当たりのワーカースペースに社員数を乗じての賃貸面積の算出でよいのか」(仲介大手)とテナント企業が不動産会社に足を運び相談することが珍しくなくなった中で、新規供給が過剰感を高めて市況悪化につながらないか。
モルガン・スタンレーMUFG証券の竹村淳郎アナリストは、「向こう5年間で市況が一段と悪化する余地は小さい。22年末に向けて改善傾向で推移すると見込んでいる」と話す。23年以降に実質GDP伸び率が0.7%ほどに鈍化したとしてもおおむね横ばいの見通しだ。20年は既存ストックの4.2%に相当する大量供給があったが、21年と22年は過去最低水準の1.2%が続く。
同証券では、需要の増減と相関関係の強いGDP予想を使って調べ、需要面積は拡大基調をたどると見通す。だが、「東京都心5区について潜在的には8%ほど需要面積が減少するとはじき、向こう5年間でそれが顕在化する」とも指摘する。在宅勤務の余波がじわりと及ぶ。
もっとも、床を返す動きはエリアやテナントの属性などで異なる。リーマン・ショックと違い一様に悪化せず優勝劣敗がはっきりする。
JLLが9月中旬に開催した「不動産&ホテル投資フォーラム」でのパネルディスカッション。野村不動産執行役員の井戸規昭氏は、「オフィスの新規開設や拡張移転の企業が増えている。当社が得意とする中規模は中小企業から増床ニーズがある」と述べた。JR西日本プロパティーズ執行役員の鈴木健司氏は、「保有するビルは100坪に満たないが動きは活発だ。テナントの入れ替えはもちろんあるが稼働率は満床に近い」と現状を説明した。
JLL日本の根岸憲一執行役員は、新型コロナで世界最大の感染者と死者を出した米国の現状について、「アメリカはオフィス賃貸借契約で長期リースを結ぶが、サブリースを可能とする契約が多い。昨年は転貸市場に出ることが多かったが、最近は自社で使うケースが増えた。オフィス市況が回復に向かっているサインであろう」と見ている。
オフィスは投資対象の主力商品でもある。その魅力は衰えていない。特に外資は環境さえ整えば資金を投じる。
前述の竹村氏は、「当社のマクロチームでは来年6月末までに米国の金利は2%になると予測している」と言い、世界金利高を意識すると低金利が続く日本は安定的な市場としてリスクマネーを引きつける。現状は需要減退ではなくシクリカル(循環的な景気変動)な市場の動きだとする。ただ、直近の日銀短観を見ると、中小企業に対する不動産向け融資にブレーキがかかっている。不動産への潤沢な資金流入が巻き戻せば市況悪化シナリオが意識される。
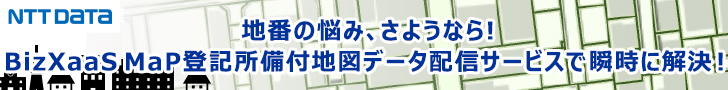

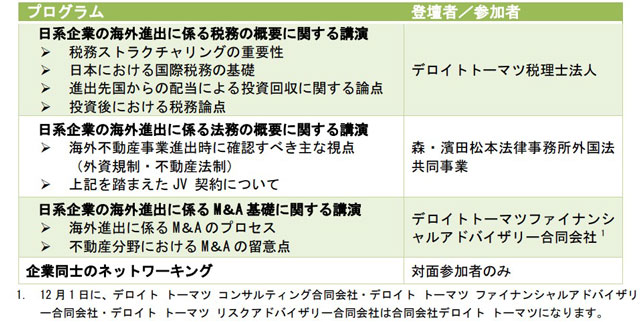














1763000967.jpg)
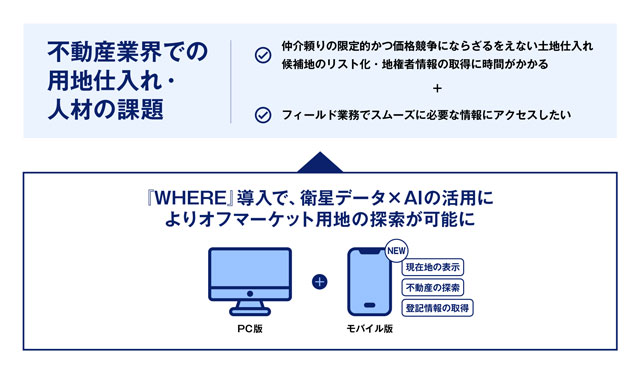

.jpg)