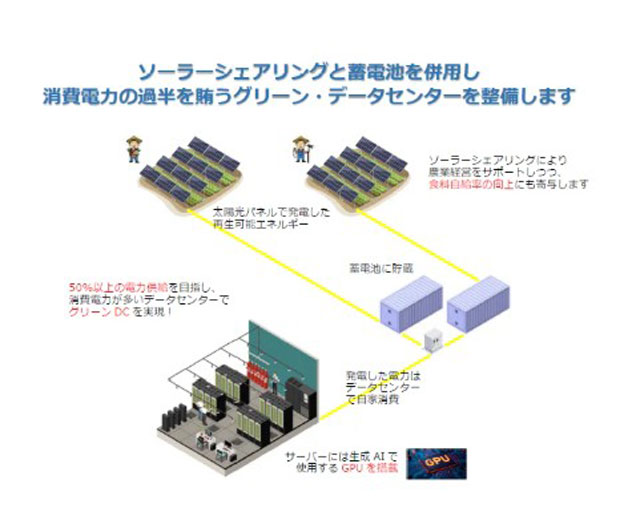Jリートは引き続き成長する。こうした見立ては、今や不動産業界関係者にとどまらない。現在の62銘柄のスポンサー企業を見れば明らかで、不動産大手だけでなく、総合商社や物流、リゾートなどあらゆる業種業態が相次いでリートビジネスに参入している。投資口(株に相当)の売買には外資や生損保、運用難に悩む地銀など機関投資家が存在感を放っている。時価総額は約17.6兆円に達する。
■ □ ■
全体で毎年1兆円前後の運用資産を購入しているが、国内の投資適格不動産の市場規模から判断して拡大余地は大きい。成長のポイントは不動産の購買力だ。つまり、エクイティが集められ、デッドが途切れない資金調達力が成長を左右する。これまでに金融庁もJリートの制度改正で既存株主に新株予約権を無償で割り当てるライツ・イシューやCB(転換社債型投資法人債)の発行を解禁するなど資金調達の多様化で市場拡大を後押ししてきた。
一方でヘッジファンドや外資、生保など機関投資家からは、「国内の不動産で賃料増額に伴うインターナルグロース(内部成長)はあまり期待できない。マクロ的に人口が減っている中でストック産業としての不動産事業は見通しとして明るくないのかもしれない」との声も漏れ伝わる。
●主力商品にコロナの影
投資対象の選別が厳しさを増すのは必至の情勢だ。足元では新型コロナ感染によるリモートワーク拡大がJリートの主力商品であるオフィスビルに悪影響を及ぼしている。テナントが床を返上する動きが顕在化しているなど、「社会構造の変化を踏まえれば、賃料の上昇圧力が強い好景気であっても欧米並みの上昇幅を見込みづらい」といった見方も少なからず散見する。
実際、直近8月に発表した主要なオフィス型リートの6月期決算は次期(21年12月期)も空室率の上昇が続く見込みだ。大口テナントの退去などが影響しており、向こう1年では空室率が頭打ちに向かうとするものの、収益改善はなお力強さを欠く見通しだ。
日本ビルファンド投資法人が1口当たりの分配金(DPU)を大型物件の取引など売却益で底上げするなどで増配につなげたことは内部成長が厳しい環境に置かれていることを物語っている。
そもそもJリートの成長ドライバーは運用資産を拡大することだ。ポートフォリオを大きくすることで1口当たりの分配金を増やし、投資家を引き付けることが宿命となっている。そして、運用物件の良しあしが明暗を分ける。
運用戦略は、前述したようにエクイティとデッドという両輪のファイナンスが鍵を握っているが、資金調達で銀行から借り入れをしてレバレッジ(負債比率)を上げたら投資口の募集(公募増資)に頼ってレバレッジを下げなければならない繰り返し。
格付け大手は、「我々は保守的な運営を継続できるのかが大きな関心事だ」と財務戦略を重視していると強調する。物件からのキャッシュフローの安定性や個別物件の価格・流動性・競争力をつぶさに分析して格付けに反映していく。投資法人債の格付けにも影響する。
●懸念は払拭できたか
もちろん、ポートフォリオの精査を怠れば金融機関や格付け会社からの評価を落とすだけでなく、投資家からのバッシングを覚悟しなければならないが、特に市場創設からの投資家の懸念が利益相反だ。例えば、スポンサーの不動産会社から相場よりも安く運用物件を購入すればスポンサーの株主が「安すぎる」、相場よりも高く購入すればJリートの投資主(株主)が「高すぎる」と不満が募る。
●調整弁になってないか 米国が震源地となったサブプライムローン問題に端を発したリーマン・ショック。この世界金融危機は金融市場の信用収縮を招き不動産各社を直撃し、業績が数百億円単位の赤字に転落した不動産大手があったものの翌年には黒字に転換した。だが、本来なら保有・運用するべき、手放すべき物件ではなかったのに系列のリートに売却して業績をつくったとの批判を浴びた。 別のケースでは、「SクラスのオフィスビルではないのにSクラスとして購入した」と海外投資家は「失望している」と不満を隠さなかった。
リーマン・ショック後に外部成長に欠かせない公募増資(PO)が相次いだが、「これまでに増資で買った物件に価格交渉の形跡が見られない」といった投資家からの批判が攻めの運用に転じる姿勢に対する好感を上回っていた。
業界関係者は、運用会社は極めて高い意思決定を法律上求められ、仕組み上も利益相反的な動きをけん制する作用が働いているとするものの、ゆがんだ形でスポンサーの調整弁であったり、物件処分の最終地みたいになる懸念は依然つきまとい続けている。