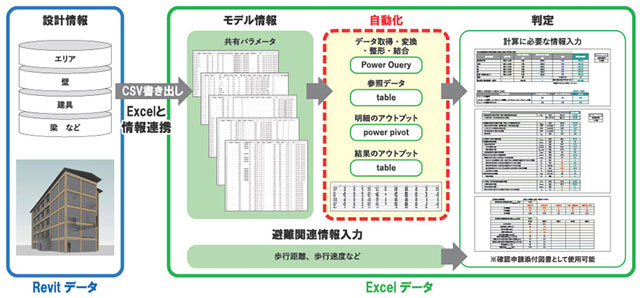住宅新報社が住宅・不動産業界経営トップを対象に実施している恒例の「新年景況アンケート」によると、全体経済、市場動向とも18年は前年より改善傾向と見る経営者が大勢を占めた。大企業と中小企業、大都市と地方による景況感の格差や二極化傾向が進展する中でも、全体的には前向きに捉えている表れである。新年会でも、株価上昇と業績の堅調さを受け、各会場とも明るいムードに包まれていた。そうした期待に違わない年になってほしいものだ。
景況アンケートによると、経済全体の見通しでは、「前年より改善(少し改善含む)する」とした経営者が52%と過半数を占め、残り48%は「前年並み」と答え、全体的には成長軌道が続く方向で捉えている。また、不動産・住宅市場の景況見通しでは「前年と同様」が全体の4分の3を占める一方、「好転」(14%)が「厳しくなる」(10%)を上回った。ここにも改善への期待が大きいことが表れた。
17年の景況については、新設住宅着工を支えてきた貸家が減速し、価格上昇で売れ行きが鈍った分譲マンション、再開発ラッシュで供給過剰が懸念されるビル賃貸市場など、数年来指摘されている課題は改善されたとはいえないが、大手不動産各社の今年度決算見込みが過去最高水準にあることを考え合わせると、全体的には追い風が続いた年だったと言えるだろう。変化をもたらしそうなのが、19年10月に控えた「消費税率の引き上げ」だ。駆け込み需要の発生とそれに伴う反動減は業界にとって死活問題となりかねない。まず、その対策が必要だ。
長続きしない「適温」
折から、株価は二十数年ぶりの高値となるなど、バブル崩壊の余韻のあった90年代半ばや、ミニバブルといわれた05年頃の投資ブームを思わせる高値水準にある。底堅い経済状況をエコノミストらは「適温相場」と呼び、今後も底堅さと拡大基調が続くとの強気予想が目立っている。だが、「適温」は経済循環サイクルから見ると、本来長続きするものではないだろう。株価も「山高ければ谷深し」で、過信は禁物である。
住宅・不動産業界の収益を支えているのは根強い需要に対応したハード、ソフト両面の商品・サービスの提供である。人口減少社会が到来し、今後住宅需要の絶対量の減少と多様化の進展が見込まれる。また、ITとAI技術の進化で商業施設やオフィスなどに関係したビジネスとリアル不動産のあり方が変わってくることも予想される。
短期的にも安定的な収益を確保することはもちろんだが、中長期的な社会経済の変化と市場構造の変化を見極めた対応が求められてくる。その備えとは、既存事業や新規事業の開拓による事業収益力の強化、財務体質の改善と強化、そして将来を担う人材の育成である。その備えが一段と進む年としたい。