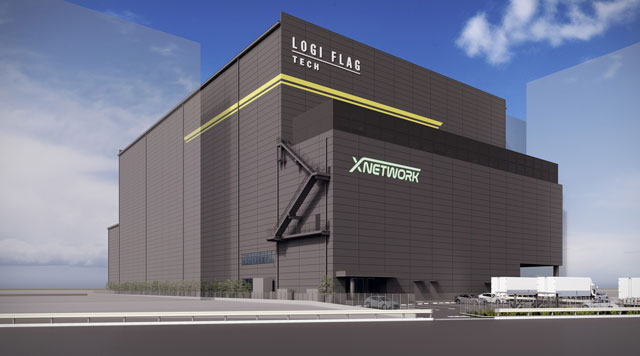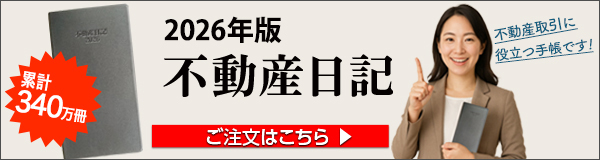本紙の前回社説(6月6日号)では、今後の住宅市場の成長には新築と中古の垣根をなくし両市場の連携こそが必要だと主張した。 更に加えれば成熟社会を迎えた今日、欠かせないのが賃貸と持ち家(分譲住宅)の新たな位置付けである。従来の〝住宅すごろく〟のように、仮住まいとしての賃貸から、いずれは本格的なマイホームへといった一方向的な流れを前提とするものではなく、また住宅の資産性に注目した〝所有本位〟の考え方を優先させるものでもない。
90年代初頭の平成バブル崩壊以降、マイホームの資産性が大きく揺らぎ始めてしまったことは論をまたない。不動産流通経営協会が毎年実施している消費者動向調査によれば首都圏で16年度中にマイホームを売却した人の平均売却損は1055万円だった。10年以降に従前住宅を取得していたケース(保有期間6年以内)に限っても平均324万円の売却損が発生している。ましてや、これから先の住宅取得はよほど慎重でなければならない。少子化・人口減少・超高齢化が長期にわたって進行する中で、最長35年の住宅ローンを返済したあとの資産価値がどうなるか、誰も予測できないはずだ。
それならば、これからの住まいの選択は、賃貸か持ち家かの判断を従来の価値観に委ねるのではなく、あくまでも自らの人生設計やライフスタイルにかなったものかどうかという自分なりの〝住まい観〟を重視すべきである。
例えば、これまでは子供の成長期にマイホームを購入するケースが多かった。それは、将来の資産価値に期待する以前に賃貸市場に子育て向けの広い住まいが少ないという実態が大きく影響していた。しかし今後は、資産価値に期待するどころか、30~40年後にはマイナス資産となる可能性さえあると識者が指摘している。
しかも子育て期間は意外に短い。子供が独立したあとは子育て期間よりも長い年月を夫婦2人、もしくは1人で暮らさなければならない。であれば、そうした子育てに適した良質な賃貸住宅が今後市場に数多く供給されるようになると、ユーザーの選択は大きく変わってくる。子育て期間は人生に様々な出来事が起こる激動期でもある。その後迎える安定期にこそ、じっくりとマイホーム選びをするほうが合理的ではないか。そうしたシニア向けのマイホームには、短い住宅ローンが前提となるだろう。
業界が目指すべきは、成熟した日本社会におけるそうしたユーザー側の新たなニーズをすくい上げることである。従来の延長線上で、供給戸数の拡大やそのためのシェア争いに力を入れることではない。ましてや効率重視のためにターゲットを富裕層に絞り込むことでもない。平均寿命の延伸と家族形態の多様化で〝住宅すごろく〟の絵図自体が多様化し始めていることに留意すべきである。