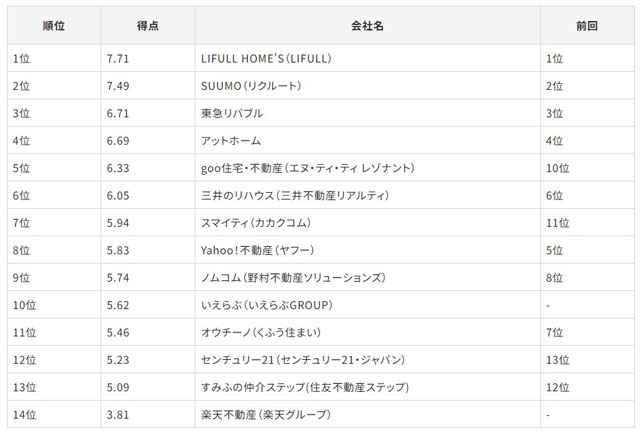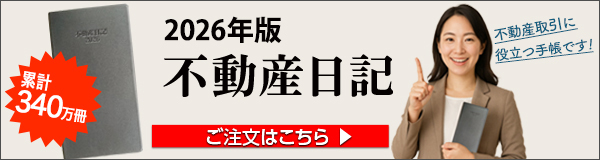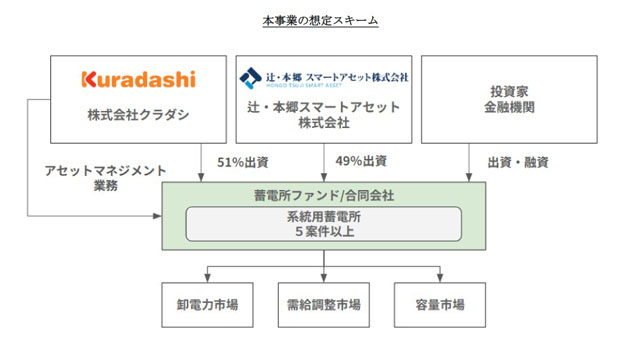取材とは材料を集めること。集めた材料をどう料理するかが記者の腕の見せどころだ。どんな仕事にもプロとしての腕の見せどころがある。そうした様々な仕事の粋(すい)を取材する新聞記者という仕事を多くの先輩たちは「記者ほど面白い仕事はない」と表現してきた。
一方、日本では「株屋」「不動産屋」「聞屋(ブンヤ)」と言われた時代があり、新聞記者もさげすまれた職業の一つだった。まして業界紙といえばブラックジャーナリズムの代名詞となっていた時代もある。また職業を「正業(実業)」と「虚業」に分ける言い方があるが、記者を勝手に書きまくる横柄な存在と見れば後者に属することになるだろう。しかし、時代は変わった――。
今でも町場の小さな不動産会社を「不動産屋」と呼ぶことがあるが、職業の社会的信用に企業規模は関係ない。また、まっとうな仕事(正業)か、そうでないかを決めるのは企業の看板や建て前ではなく、そこで働く社員一人ひとりの潔白な気構えである。だからこそ不動産業界紙は今こそ規模や建て前ではなく、不動産会社の本質に迫り、同じ気構えの経営者や社員と連携し不動産業の最終地点を共有すべき歴史的転換点を迎えている。
奇しくも不動産業と業界紙発行の二刀流で知られる宮地忠継氏(耶馬台コーポレーション社長、全国貸地貸家協会新聞編集長)はこう語る。
「不動産業は幅広く、また奥が深い。不動産というものは人々のより豊かな人生、様々な可能性を具現化するものだからだ。それだけに捉えるべき題材はいくらでもあるのだが、それをどういう視点で書くかが重要だ。ただ、その対象そのものは時代と共に変わる。コロナ禍での不動産需要の変化はそれを語っている。また、多くの不動産会社は事務作業機械化の必要性を強く感じているが、ITやDXは本質的にはもっと大きなものに奉仕するものではないかとも考えている。だから、業界紙に対する不動産業者の要望は、そういう諸々のことを考えるための指針、どこに人々の希望と業界に対する不満があるのか、どこにまだ我々の分かっていない世界があるかという点についての示唆を与えてほしいということだ。例えば住宅の広さやデザインなどに関する嗜好の変化、これからの街の趨勢、そういうことについて一定の哲学的な観点も含んだ奥深い記事であれば、ランチを食べるよりも新聞を読むのが楽しみになる」。
人を信じる 宮地氏のコメントは我々業界紙の人間を勇気づけてくれる。そして同じ気構えの同志は必ず居ると感じる。先に、日本の不動産業と業界紙の関係が歴史的転換点にあると言ったのは、ユーザーの関心が不動産会社の規模や建て前(看板)ではなく、経営理念の本気度、個々の営業担当者の実力、志の高さといったものに向かい始めたことを指す。その重要な変革期において、不動産業界紙はどうあるべきだろうか。当たり前だと思っていたことを問い直す視点も必要ではないか。
例えば、同じ媒介報酬額を払うのであれば、買主は〝仲介人〟よりも〝エージェント〟を求めるのが当然ではないか。単独仲介はそれが難しいが、共同仲介でも〝仲介〟である以上は買主側営業担当者の最優先事項も契約締結にある。そのため、買主は「本当に私のために場合によっては契約断念も含めて相手とギリギリの交渉をしてくれたのだろうか」という疑念を払しょくしきれない。
とはいえ、ではエージェント制ならば本当に信頼して任せることができるのだろうか。そのエージェントの得意分野も契約実績も本人の自己申告に過ぎないとすれば…。ましてや、「誠心誠意尽くしてくれたのか」といった部分は証明のしようがない。米国では既存客からの紹介が多いというが、営業担当者も人間である以上そのときの体調もあるだろうし、クライアントとの相性の善し悪しもある。つまり最後は、人間は人間を信じるしかない。そして人間には人間の信頼に応えたいという熱情がある。宮地氏が指摘した哲学的観点とはそうしたことではないだろうか。