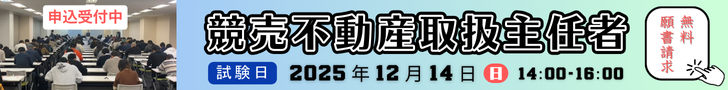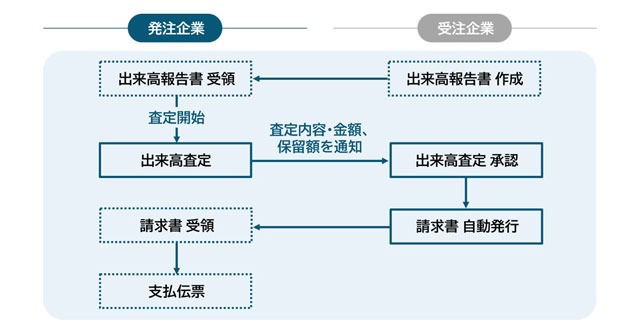今年2月から始まった東京都の人口減少(対前年同月比)が止まらない。人口の変動要因は自然増減と社会増減に分かれるが、昨年7月以降の社会減(転入者<転出者)が効いている。自然減(出生数<死亡数)は既に16年から始まっている。転出者の増加はコロナを背景にした働き方改革と住まい方改革の影響がいかに大きいかを物語っている。
東京都の人口を対前年同月比で見ると、今年2月にマイナス662人と初めて減少に転じて以降は3月(9767人)、4月(2万5443人)、5月(3万9917人)、6月(4万1591人)、7月(3万9832人)、8月(4万1263人)、9月(3万6106人)と8カ月連続の減少となっている。
都の総人口から見れば減少幅は微々たるものだが(9月で0.25%)、4万人と言えば長野県小諸市の人口に匹敵し、3万6000人という規模は千葉県南房総市の人口を上回る。
人口が減少に転じた最大の要因は、コロナ感染の流行を背景に昨年4月以降の転入者減少と8月以降の転出者増加だ。転出超過は昨年7月から基調化し、今年2月まで続いた。入学・就職期の3、4月は転入超過に戻ったものの、5月から7月は再び3カ月連続で転出超となった。ここにきてコロナ感染者が急減していることからこれがどう影響するかが注目される。仮に、社会増減がコロナ以前の状態(12カ月移動平均で月6000~7000人の転入超過)に戻れば、東京の人口は再び増加に転じる可能性が高い。
それはともかく、東京の人口が8カ月にもわたって減少に転じたショックは大きい。戦争などの特殊要因を除けば、1868年、江戸が東京(東の京)と改称されて以来の異変と思われる。異変の兆候は小さいものの、その示唆するところは大きい。不動産業界としてもそろそろこれまでの発想やビジネスモデルを改め、新たな価値観を模索するときではないだろうか。
本務は価値創造
不動産協会が日本ビルヂング協会連合会と共に今年4月に策定した「不動産業における脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」に注目しよう。
そこには、2050年の社会像に向けた不動産価値の変化を象徴する建物として(1)分散型オフィス、(2)職住一体型住宅、(3)シェアハウス、シェアオフィスの3つが挙げられている。(1)と(2)は働き方改革の進展で、ワーカーの働く「時間」と「場所」の自由化が更に進むと見ている証拠だ。(3)は脱炭素化に向け住む場所も働く場所もエネルギーの省力化が必須ということだろう。
日本シェアハウス協会代表理事の山本久雄氏もこう語る。「シェアハウスはこれまでシェアエコノミーの観点から語られることが多かったが、今後は省エネ型のライフスタイルとして注目されることになるだろう。人類最重要課題の地球温暖化防止に貢献できる居住形態として、その普及に全力を尽くしたい」
不動産業はいまだに古いビジネスモデルのまま、と折に触れ言われ続けてきた。それはなぜなのかと考えてみると、結局90年代初頭のバブル崩壊後も東京の人口が増え続けてきたことが大きいように思う。不動産価格は人口動態と密接に関わっているから、東京ではバブルが崩壊した後も、大本では右肩上がり時代の慣習が残り続けたということではないか。それはそれで一つの見識だが、問題はこれからだ。
不動産業の本務は〝価値創造〟にある。端(はな)から価値があるところで利益を上げるのはたやすいが、不動産の隠された可能性を引き出し具現化できるのは本当のプロにしかできないことだ。その意味で人口減少時代にこそ不動産業の本領が発揮されなければならない。
08年のリーマンショック以降、首都圏ではマンションディベロッパーの数が激減した。つまり、市場が大きく縮小すれば本物のプロしかプレーヤーとして生き残れないということである。