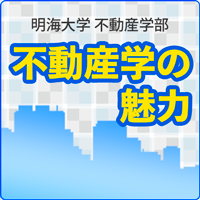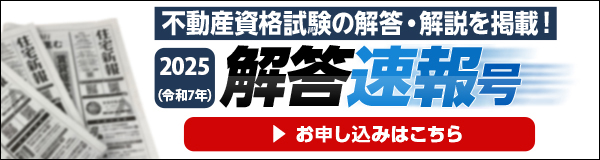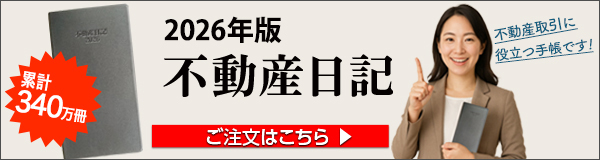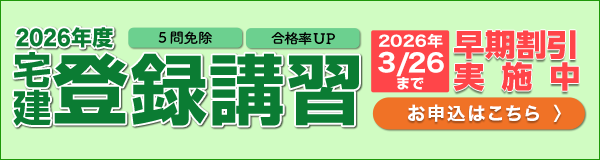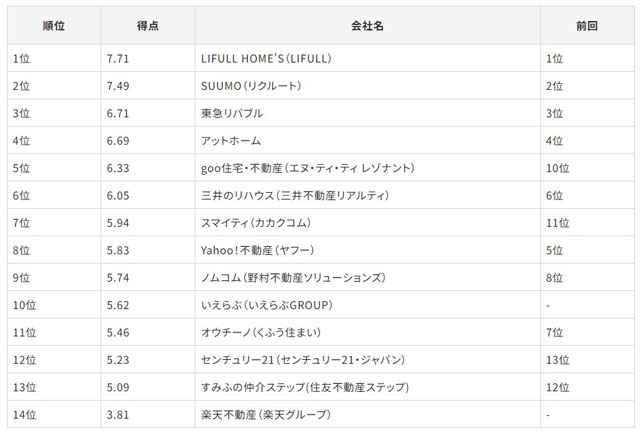不動産学の魅力 明海大学不動産学部 記事一覧
-
不動産学の魅力 バレエと不動産学 舞台から学んだ不動産学の本質 明海大学 不動産学部 第78回
私は14年間クラシックバレエを続けてきた。舞台上では、照明の位置、背景の奥行き、ダンサーの立ち位置といった一つひとつの要素が、観客の視線や感情の流れを左右する。そこでは、空間の設計が「人の動き」と「心(続く) -
不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第77回 不動産テックの進展とその社会的影響 効率化だけでなく価値観を再定義
不動産テックとは、AIなどの先端技術を不動産の分野に応用する取り組みの総称である。不動産の価値や取引の構造、更には都市の在り方までも変えつつある点で興味深い。特に注目しているのは、ブロックチェーン技術(続く) -
不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第76回 京島に息づく長屋文化 空き家活用がつなぐ人とまちの絆
ゼミ活動で「遊休不動産の有効活用」をテーマに、現地調査で東京都墨田区京島を訪れた。戦時中の火災を免れた数少ない下町の一つで、昭和初期の「木造長屋」が今も多く立ち並ぶ地域である。密集した細い路地や、住(続く) -
不動産学の魅力 第75回 明海大学 不動産学部 REITと不動産企業株式の魅力 投資の分析力を磨く糧に
不動産投資には、現物不動産の購入、不動産企業の株式取得、REITなどの方法がある。その中でも、少額から始められるREITや不動産株式は、個人投資家にとって現実的な選択肢だと考える。自らもREIT投資を実践してお(続く) -
不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第74回 リノベ 空き家・空き施設活用 人が集まり経済活動が活性化
授業の一環で空き家・空き施設の活用について調べ、その中で特にリノベーションによる活用について興味をもった。近年空き家は増加傾向にあり、様々な社会問題をもたらしている。国土交通省によると、全国の空き家(続く) -
不動産学の魅力 ダイヤ改正が不動産市場に及ぼす影響 京葉線沿線の住宅価格が約5%低下 明海大学 不動産学部 第73回
少子高齢化が進展している日本では、地方や郊外部で公共交通機関の縮小が起きている。交通利便性の低下は、そこに居住した場合の移動費用を上昇させるため、不動産市場に何らかの影響をおよぼすと考えられる。(続く) -
不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第72回 福岡の不動産高騰と学生の生活 成長都市の姿と、そこで暮らす現実
福岡の街は、今、急速に変わりつつある。25(令和7)年の公示地価では、住宅地の上昇率が全国3位、福岡市に限れば前年比9%と全国トップレベルの上昇率を示した。ニュースでは「経済の活気」として取り上げられるが、(続く) -
不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第71回 社会実践教育体験記 多角的視点で地域資源を磨く
幼少期から私は間取りやインテリアに興味を持ち、郵便受けに入った住宅情報チラシをよく集めていた。幼少期から興味のあった「家」や「まち」について専門的に学べるという点と「日本で唯一の不動産学部」という点(続く) -
不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第70回 シティホテルの経営と資産価値 高級感と親しみのバランス鍵に
オリエンタルホテル東京ベイの外観は、都会的でありながら温かみのある印象を受けた。シンプルで落ち着いたデザインは、ビジネス利用者にも家族連れにも配慮されたもので、駅直結というアクセスの良さと相まって、(続く) -
不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第69回 不動産業界の未来 限定提供データの活用が変える
不動産業界ではAIやビッグデータを活用したデジタル変革(Digital Transformation=DX)が進んでいる。特に、特定の者に提供される非公開の営業情報のことを指す限定提供データの活用が不動産業界の業務効率や顧客サ(続く) -
不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第68回 生活ルールを全入居者に徹底を 集合住宅 賃借人同士の騒音トラブル
集合住宅における騒音トラブルは、賃貸人・賃借人双方にとって深刻な問題だ。賃借人同士で騒音トラブルが起きても、賃貸人が気づかないこともある。賃貸人をA、賃借人をBとCとし、BがCからの騒音に悩まされている(続く) -
不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第67回 不動産学との意外な接点 音楽の「場」をつくる力ー
私は音楽活動を通じて、「人が集まる場所」には特有のエネルギーが宿ることを肌で感じてきた。 高校・大学とバンド活動に打ち込み、路上ライブにも挑戦してきた中で、ある商店街での演奏経験が特に印象に(続く) -
不動産学の魅力 明海大学不動産学部 第66回 不動産とサウンドスケープ 質の高い空間を「音」が創る
不動産には建物や土地という印象が強くあるが、広く捉えれば「人が暮らし、活動する空間そのもの」を指すと言える。建物や土地といった物理的な構造だけでなく、そこに流れる時間、空気、光、そして〝音〟といった(続く) -
不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第65回 ドア、どーあく ? ドアを新しい視点で考える
不動産学部では2年生から設計演習がスタートする。学年が上がるにつれ、街並みや共有地マネジメントを意識した約50戸の住宅地計画やホテル不動産の開発企画書作成を行うが、その最初の一歩として、作図の基礎的技(続く) -
不動産学の魅力 「不動産を動かす」 キープ&チェンジ時代の曳屋 明海大学 不動産学部 第64回
「曳屋」とは、建物を解体せずにそのままの状態で移動させる建築工法である。私が「曳屋」を初めて知ったのは、テレビ番組で古民家再生プロジェクトを見たときだった。建物は不動産、つまり土地に定着するものだと(続く) -
不動産学の魅力 EV車充電スタンドを設置する問題点 分譲マンション対応が課題 明海大学 不動産学部 第63回
日本では2035年までにガソリン車の新車が販売終了になる予定だ。今はまだガソリンスタンドの方が多いが、国は「電気自動車等の車両の普及と充電インフラの整備は、両輪で進めていくことが必要」としていて、今後は(続く) -
不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第62回 住まいの価値と維持管理の工夫 築年数で測れない面白さ実感
大学の授業の一環で、神奈川県にあるH団地を見学した。H団地は1970年代に日本住宅公団から分譲された600戸からなる高経年団地型マンションである。H団地の住棟は階段室型5階建てであり、エレベーターが設置されて(続く) -
不動産学の魅力 第61回 明海大学不動産学部 防災集団移転促進事業 自分ごとで地域の将来を捉える
6月末に大洗町が開催した第4回「防災まちづくりワークショップ」に参加した。茨城県大洗町の堀割・五反田地区では、72戸を対象に防災集団移転促進事業(以下、「防集事業」)が進んでいる。 防集事業は、災害発生地(続く) -
不動産学の魅力 第60回 学校統廃合による不動産需要の変化 持続的な発展を可能とする
少子化の影響で学校の統廃合が年々増加していることを知った。文部科学省の学校基本調査によるとここ20年間で5938校の公立小中学校が廃校になっている。学校統廃合が統廃合対象地域の不動産需要に与える影響(続く) -
不動産学の魅力 日常の街並みの意味 見世蔵と間口税の関係で知る 明海大学 不動産学部 第59回
2年次に履修した都市計画の授業で、「見世蔵」と「間口税」の関係について知る機会があった。「見世蔵」は、江戸時代に多く建てられた日本の伝統的な建築様式の一つで、商家や店舗として利用される土蔵のことをい(続く)