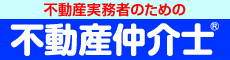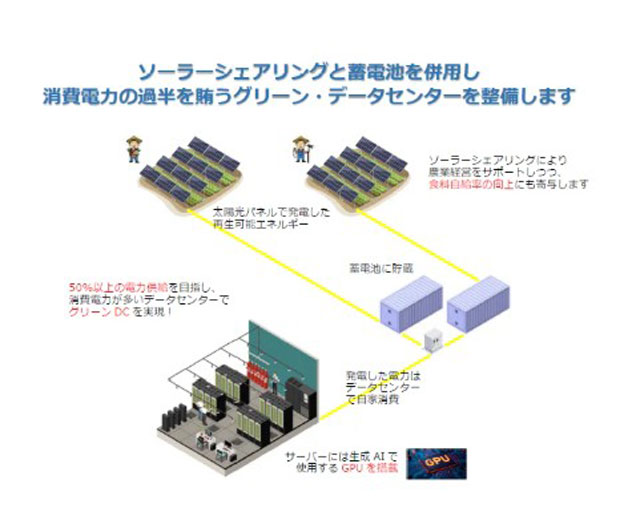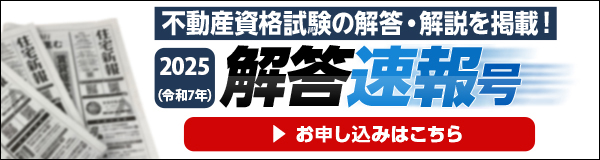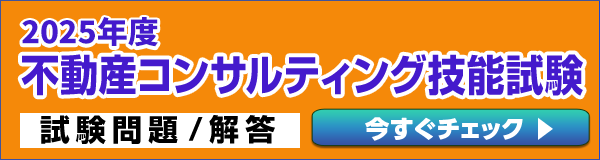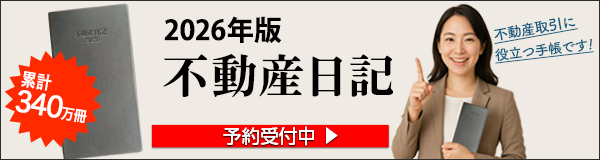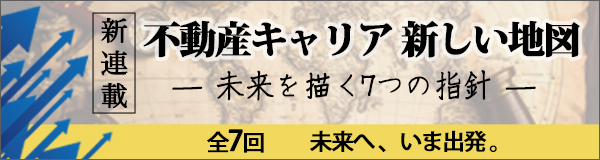不動産キャリア 新しい地図 ― 未来を描く7つの指針 ― 第3回
AIが台頭し、社会構造が変わりゆく中で、不動産業界に求められる人材像も大きく変化しています。単なる「資格保持者」ではなく、時代の変化を読み解き、顧客の人生に寄り添える真のプロフェッショナルへ。
本連載は、不確実な未来を乗り越えるための「新しい地図」。全7回で、あなたのキャリアデザインをサポートします。
不動産ライター 大槻一敬
次世代不動産の価値創造 ~社会課題解決で差別化を図る~
人口減少と高齢化が進み、社会の課題が複雑化する現代において、従来型の「収益重視の不動産経営」だけでは持続的な価値を生み出すことが難しくなっています。次世代の不動産に求められるのは、“社会課題の解決を通じて価値を創造する”という新しい発想です。高齢者や子育て世帯、外国人など多様な人々が共に暮らし、地域が再び活力を取り戻す。その舞台となるのが「社会価値を内包した不動産」です。

1.高齢化社会に対応する“やさしい住まい”づくり
日本はすでに人口の約3割が65歳以上という超高齢社会を迎えています。段差をなくしたバリアフリー設計や、手すりやスロープの配置、広めのトイレや浴室スペースなど、ユニバーサルデザインへの対応はもはや特別な仕様ではありません。今後は「自立支援」と「共生」の視点も重要になります。例えば、介護施設と一般賃貸を複合させた“混住型レジデンス”や、IoTセンサーによる見守りシステムを備えたスマートホームの普及が進むでしょう。高齢者の「安心」と、家族の「負担軽減」を両立する仕組みを整えることが、不動産価値の維持・向上につながるといえます。
2.地域コミュニティの再生と交流拠点の創出
かつての住宅地には「助け合い」「見守り」といった自然なつながりが存在しました。しかし現代の都市部では、単身世帯の増加とともに地域の“人のつながり”が希薄になっています。ここにこそ、次世代不動産の新たな価値があります。
マンションの共用ラウンジや屋上テラスを「地域サロン」として開放したり、空き店舗を地域イベントや子ども食堂の会場として活用したりする取り組みが注目されています。管理組合・オーナー・地域NPOが連携し、建物を“まちのハブ”として再定義することで、単なる住居から「交流・支え合いの場」へと進化させることができるのです。
3.空き家問題とまちづくりの専門的アプローチ
全国で空き家は約900万戸を超え、地方では「集落の空洞化」という深刻な課題に直面しています。こうした中、行政任せでは解決が難しい空き家活用において、不動産専門家の役割がより重要になっています。建築士・司法書士・社会福祉士などの専門家と連携し、地域の将来像に基づく再生計画を立案するケースが増えています。たとえば、老朽家屋をリノベーションして地域カフェやコワーキングスペースへ転用する事例、空き家を学生・高齢者の共生住宅に改修するプロジェクトなどもあります。
「使われない不動産」を「地域を動かす不動産」へと変えるには、単なるリフォームではなく、“まちづくりの視点をもった再生”が欠かせません。不動産業はもはや“仲介業”ではなく、“地域経営業”へと進化しつつあるといえるでしょう。
4.社会課題に対応する専門性の証明と信頼性の時代
近年、不動産分野でも専門資格の重要性が増しています。宅地建物取引士(宅建士)や賃貸不動産経営管理士に加え、様々な専門性を持った民間資格も注目されています。社会課題に対応できる不動産人材とは、単に法律や取引の知識を持つだけでなく、「社会的意義のある提案」ができる専門家です。高齢者や障がい者、子育て世帯、外国人、地方移住者など、多様なニーズを理解し、法務・建築・福祉・金融を横断的に扱える人材こそが信頼される時代になっていきます。資格は単なる肩書きではなく、社会への“約束”であり、“責任の証明”です。不動産業の信頼性を高めるには、個々の専門家が倫理観と使命感を持って地域に貢献することが欠かせないのです。
※第4回「デジタルマーケティング×不動産~顧客との新しい接点創造~」 11月下旬公開予定