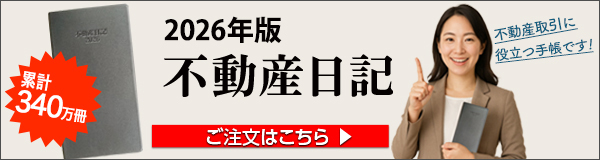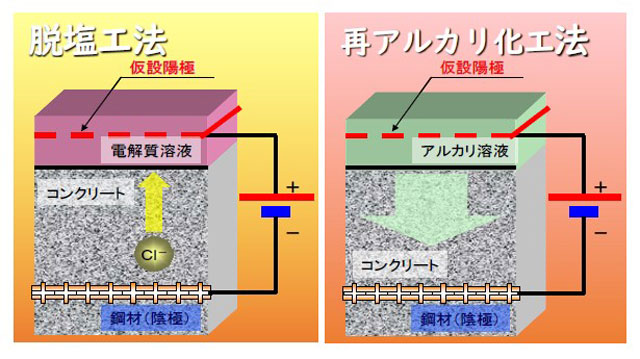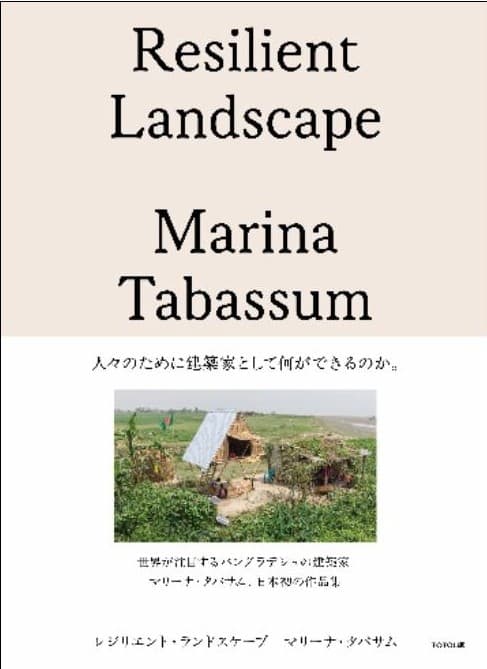庶民という言葉には力がない。もしかしたら、自分を庶民だと思っている日本人は一人もいないのではないか。
つまり、死語に近い。80年代後半のバブル経済時代には〝一億総中流〟という言葉が流行ったが、中流と庶民とはニュアンスが違う。中流は単に所得水準のことだが、庶民という言葉には特権階級に対する一般市民(平民)としての誇り(連帯意識)が含まれている。庶民という言葉が今や死語になりつつあるのだとすれば、国民の間に〝分断〟が生じているということを意味しないか。
◇ ◇
昨今の東京の住宅価格高騰は〝庶民〟感覚からずれている。不動産経済研究所によると、21年に売り出された首都圏の新築マンションの平均価格は6260万円でバブル期の最高値6123万円を上回り過去最高となった。東京カンテイの調査によれば、東京都では新築は平均年収の13.04倍、中古でも11.50倍となっている。
不思議なのはそのこと自体が近年はあまり問題にされないことだ。バブル期には地価高騰で「サラリーマンがマイホームを持てなくなる」「それが日本人の美点だった勤労意欲を失わせる」と大騒ぎになり、NHKでは「土地は誰のものか」という特番(87年)を3週に渡って組んだぐらいである。このときと今は何が違うのだろうか。
今は超低金利と所得格差拡大を背景に35年の長期変動ローンを組めば、購入可能な人たちがそれなりにいるということである。昨今ディベロッパーが富裕層志向を強めている理由もそこにある。購入可能な層にターゲットを絞るのは各企業としては正しい戦略となる。しかし、〝合成の誤謬〟ではないが業界全体としてはどうなのか。名だたる不動産会社が一部の国民だけに目を向け、多くの庶民を切り捨てることになれば、それは不動産業界の職業倫理として許されるのか。人間にとって最も大切な基盤となる住宅という商品に関わる業界として、それで社会的責任が果たせるのだろうか。
住まいの多様化
今こそ新築か中古か、売買か賃貸かという視野を超え、住まいはどうあるべきかという見地から様々な層の国民が入居できる、しかも快適な居住環境を供給することに業界全体が総力を挙げて取り組むときである。
そうした中、大手ディベロッパーが新しい住まい方の選択肢としてアドレスホッパータイプの賃貸住宅を供給し始めたことが注目される(10月25日号4面参照)。アドレスホッパーとは定住することなく趣味や仕事に応じて住みたい場所をその都度選び、比較的短期間で居住場所を変えていく生活スタイルのこと。コロナ禍でテレワークが普及したことも背景にある。起業家向けに東京都心でコワークスペースを併設し、法人登記も可能なSOHO型賃貸住宅を供給する動きも始まっている。
一方、シェアハウス業界でも最近はコンセプト化が加速し、多様なニーズやライフスタイルに応じる物件が増えている。やや極端な例を挙げれば、東大合格をめざす人たちが短期合宿的に住む予備校機能付きのシェアハウスなども登場している。
そのほか一般の賃貸では、夜でも楽器を演奏できる完全防音のマンションやガレージハウス、ペット共生型マンションなどが人気を集めている。こうした住まいの〝拠点化〟は、これまでは持ち家取得までの仮住まい的位置に甘んじてきた我が国の賃貸住宅市場を大きく変革する可能性がある。一方、日本でも販売が始まった超ローコストの3Dプリンター住宅がこうした住まいの拠点化を見越し、実需というよりも投資物件として関心を集め始めている。
生活基盤産業ゆえに人間産業とさえもいわれる不動産業界が庶民から目をそらすことは許されない。好立地の土地取得難、建築資材の高騰、物価高、職人不足など課題山積の時代だからこそ、従来の発想を脱し、すべての国民に快適で文化的な住まいを提供するという不動産業の原点を忘れてはならない。