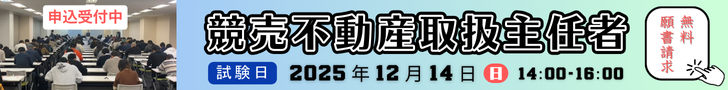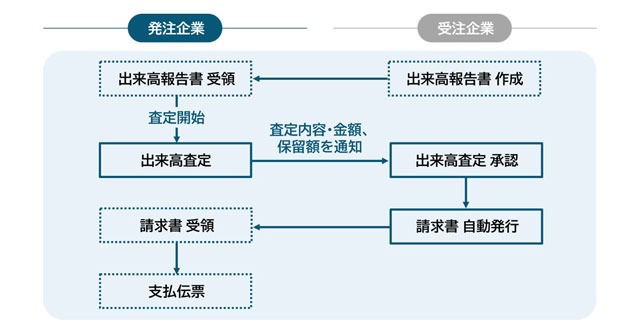「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け戸建て住宅の分野で課題となることの一つに、消費者に省エネ強化や環境貢献による価値をどのように受け入れてもらうか、ということがある。コストアップによる競争力の維持が難しくなるからだ。従来までの住宅と比較してコストアップ分を補って余る付加価値、具体的なメリットをどのように訴求できるか、今後は提案力がより重要度を増しそうだ。
国ではZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、LCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅などのハイレベルな省エネ住宅普及を掲げ、推進している。これらは一見すると、国民に分かりやすいカーボンニュートラル実現のための住宅施策のように思われる。しかし、実際はどうだろうか。例えば、ZEHは開口部を小さくしたり、大規模な創エネ設備を設置すれば、比較的容易に要件を満たすことができる。ただ、そうして完成した建物は、住まい手にとって快適なものにならず、建築意欲を刺激するものにはならない。
「快適さ」を分かりやすく
つまり、断熱・省エネ性能と快適性を併せ持つことが非常に重要になる。そうした点に着目した取り組みを行っている住宅事業者がある。「ファミリー スイート」を訴求している積水ハウスがその一例だ。その中核的な提案となる「スローリビング」は、高天井、大開口の大空間が可能であり、居心地の向上や空間活用の幅を広げ、その実例は顧客にとって快適さを非常に理解しやすいものとなっている。ちなみに、同社のZEH率は20年度に91%となり非常に高い水準だが、「ファミリー スイート」の採用率61%(21年度上期)も同様に高く、ここからより高付加価値のZEH供給に努める姿が確認できる。
一方、「エネルギー自給自足」という切り口で差別化を図ろうとしているのがセキスイハイム(積水化学工業住宅カンパニー)だ。昨年10月に発売した「新スマートパワーステーションFR グリーンモデル」は、約10キロワットの太陽光発電と1時間当たり12キロワットの新型蓄電池を搭載。これによりエネルギー自給自足率を従来型の約66%から約73%に向上させたのが特徴だ。これは、年間約260日分相当の電力を太陽光発電で賄える計算になり、更に環境負荷を低減できるという。エネルギー自給自足のみならず、余剰電力を売るより年間の光熱費を約1~3万円低減できるという経済性、更に災害で発生する停電にあたってもより日常に近い暮らしが可能になるという高いレジリエンス性という付加価値も有しているのも特徴となっている。
省エネ効果の基準を明確化
ところで、断熱は住宅全体の省エネ性能を高める重要な要素であり、現行の省エネ基準より高いレベルの住宅供給への模索も始まっている。その一つとして、学識経験者らが20年2月に立ち上げた一般社団法人「20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」による、断熱性能のグレード「HEAT(ヒート)20」の活用がある。「UA値(外皮平均熱貫流率)」に基づくもの。下のグレードからG1、G2、G3と表示し、G1は居室連続暖房による最低室温を「おおむね10度に保つこと」、G2は1.2地域を除けば「おおむね13度」、G3は「おおむね15度以上を確保すること」としている。
居室の温熱環境、冬期でも快適な室内を維持しやすく、部屋や階の間の温度むらが少ない住宅ば、住まい手の健康維持、特に高齢者の健康長寿命を長くするなどといったことが近年注目されているが、ヒート20のグレードはそれに準拠した住宅の健康への好影響を消費者に分かりやすく説明する根拠の一つとなるわけだ。
また、「平成28年省エネ基準における間歇暖房時の暖房負荷に対する全館連続暖房(24時間全館空調)とした時の暖房負荷削減率」についても明示。1.2地域で居室連続暖房を行うケースでは、G1が約20%削減、G2が約35%削減、G3が約55%削減などだ。全館連続暖房の設置により温熱環境が向上すると言われているが高価。上記はその導入の判断をする指標となり、イニシャルコストと長期的なランニングコストの関係性を示すことができ、顧客に推奨する根拠になる。
いずれにせよ今後、住まいのカーボンニュートラルを実現する上で、省エネ性や快適性について、従来よりも明確な基準やエビデンス(根拠)を示す、性能を「見える化」する努力が求められるようになり、その対応が激化する競争の中での重要な差別点になるに違いない。