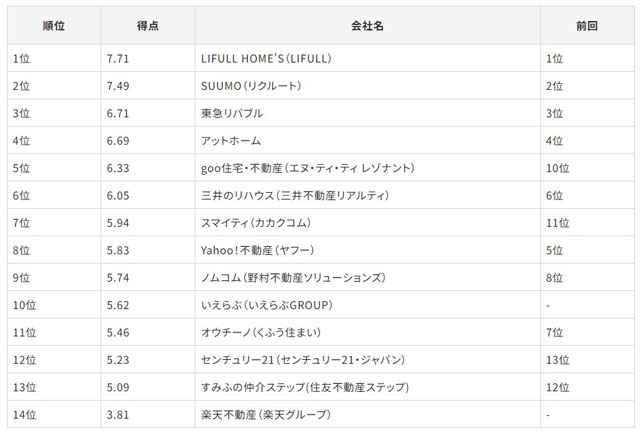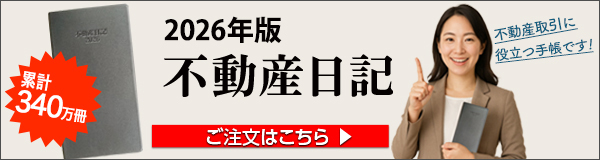新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う在宅勤務の急速な普及により、この1年半ほどの間にオフィスのあり方は大きな変化を余儀なくされた。その場合に焦点となってきたのは、主にオフィス自体の「必要/不要」や空室率といった概念だが、個別の設備や機能に対する価値観もまた変容している。今回は、特に「会議室」という存在にフォーカスして、現在の動向と今後の見通しをまとめた。(佐藤順真)
供給事業者の対応進む
結論から先に述べれば、コロナ禍により会議室は「従来とは異なった形で重要度が高まっており、またニーズの多様化への対応も強く求められている」と考えられる。
最近のオフィス等の事例を見ても、〝いわゆる会議室〟の再定義が進んでいる様子が随所で見られる。長くスタンダードなモデルとして提供されてきた「ある程度の広さの個室に、長机と複数の椅子を置いた会合用空間」という会議室の需要は縮小する可能性が高いと同時に、なんらかの機能や付加価値を備えたパブリックスペースとしての〝会議室〟は存在感を増している。背景にある主な要素は、リモートワークの増加とリアルでのコミュニケーションの不足のようだ。具体的な事例を見ていきたい。
リモート普及への対応
貸し会議室事業などを手掛けるマックスパート(東京都千代田区、片山達哉社長)は6月1日、新たにサブスクリプション型貸し会議室サービスの提供を開始。同社はその理由として、会議や商談、セミナーなどのオンライン化が進んだことで社内会議室の利用頻度が増加し、会議室不足から外部会議室の定期利用を求める顧客の声を挙げる。
また三井不動産が4月に開業したスタートアップ向けシェアオフィス「THE E.A.S.T.日本橋富沢町」では、オンライン業務の増加を見越して、共用部にオンライン会議を前提とした「ミーティングルーム」を設けている。業務のデジタル化に積極的なことの多いスタートアップ企業の需要に応えた仕様だ。
リアルな場の共有
もう一つ、コロナ禍が職場にもたらした大きな変化は、「リアルで相対する機会の減少」だ。雑談や非言語コミュニケーションの不足による弊害は、オフィスの〝集まる場〟としての役割を再確認させることとなった。
サンフロンティア不動産では、6月に東日本橋で開業した新ブランド「LIT(リット)」で、セットアップオフィスでは近年は削減傾向にあった専用会議室を、あえて全専有部に設けた。企業の文化やミッションに加え、仲間と熱意や志を共有する場として、会議室のニーズが高まっているという認識だ。
この場合の会議室では、その形は必ずしも従来型の隔離された個室に限定されない。東急不動産グループとスノーピークグループによる「キャンピングオフィス浜名湖」(4面参照)のように、オフィスとは全く異なる環境で集うというアプローチも有効だろう。イメージ的には会議〝室〟ではないかもしれないが、人が物理的に集う場という役割から見れば、同じ延長線上にある空間づくりだ。
ユニークさが不可欠に
会議室を取り巻く現状について、国内外の先進的オフィス動向に詳しい三井デザインテックのスペースデザイン事業本部ワークスタイル戦略グループ長・岡村英司氏は、「そもそもオフィスがなぜ必要なのか、という根本を考える時代となっている」と語る。そしてその答えの一つとして、「作業の場ではなく、課題解決に向けたコミュニティづくり、価値観共有の場」という考え方を示す。
オンラインアクセスの向上は社会に大きなプラスをもたらしたが、「人間の根底にあるものは当分変わらない。リアルとバーチャルの融合が進んでいく一方で、リアルの大切さが失われることはなく、より研ぎ澄まされていくだろう」と岡村氏は推測する。
それでは今後、オフィス供給事業者にはどのような対応が求められていくのか。岡村氏は「多様化するニーズに対応するため、ユニークさを示していかなければ間違いなく厳しくなる」と断言する。
変化が早く多様化の進むビジネス環境では、既存のスタイルの会議室を提供し続けていても、需要の先細りは見えている。同時にテナント企業の経営者側としても、組織運営円滑化やミッション共有の重要性を強く意識し、戦略的な投資として最適な会議室の形を選んでいくことが求められる。つまり、やや誇張して言えば、会議室を考えることはオフィスそのもののあり方を定義していく行為にもつながるのではないだろうか。



1624850013.JPG)