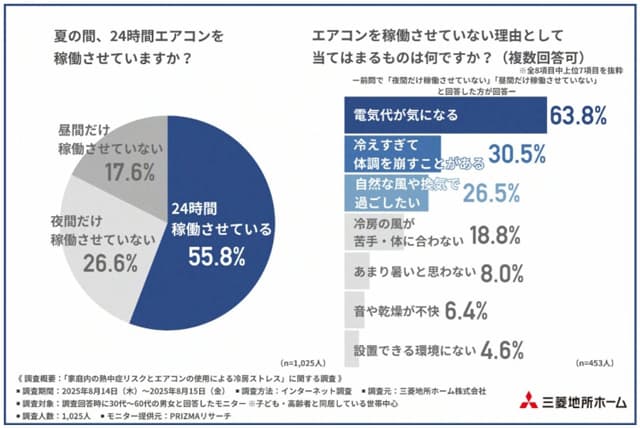東京都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷)は首都圏におけるビジネスの中心地である。この地域のオフィス市況はデータ分析の代表的なもの。各社の調査発表では対象になるビルは異なるが、都心5区の空室率は上昇基調にある。中小企業の解約、館内縮小に加え、大企業がオフィス戦略の見直しを始めており、空室率上昇の要因に変化の兆しがある。そうした背景に新型コロナウイルス感染症による在宅勤務の推奨があるのは言うまでもない。新型コロナも完全な沈静には至っておらず、予断は許されない状況だが、各社の調査資料を踏まえ、オフィス市況の背景を読み解く。(古賀和之)
20年度上半期の都心5区のオフィス市況は、オフィス面積の縮小、解約など空室率は上昇基調にある。三鬼商事が発表する平均空室率(調査対象は基準階面積が100坪以上の主要貸事務所ビル)は9月が3.43%と、7カ月連続の上昇。三幸エステートが発表する、大規模ビル(調査対象は1フロア面積200坪以上の賃貸オフィスビル)の空室率は9月が0.76%であり、2カ月連続の上昇を示している。
一方、JLLはAグレードオフィス(定義は延べ床面積で3万m2以上など)、Bグレードオフィス(定義は同5000m2以上など)で算出。9月末の空室率はAグレードが0.7%(6月末比で横ばい)、Bグレードが0.5%(同0.2ポイント上昇)と、いずれも1%を切る水準だ。JLLのリサーチ事業部ディレクターの大東雄人氏は「オフィス面積の見直しの動きは高まっているが、空室をどうするか、解約を出すかを検討している状態」と分析。Aグレードから価格帯の低いBグレードへの移行検討、本社近くのBグレードにオフィスを分散化させる動きがあり、Bグレードの空室率上昇を抑制している。ただ、大東氏は「今までのマーケットサイクルのように、Aグレードの需要が減退して賃料が下がり、その影響でBグレードが圧迫されるという、通常の動きが出てくるのでは」と推測する。
調査関係の担当者は総じてリモートワークにたけたIT・通信系のオフィス解約、館内縮小を指摘する。また、ベンチャー企業などの中小企業は判断が速く、オフィス戦略の転換も図りやすい。都心5区のうち、IT関連が集積している渋谷区の苦戦を指摘する声は多く、5区別の平均空室率を算出する三鬼商事のデータでも渋谷区は4.48%(9月)と高い数値を示す。
都心5区について、三幸エステートの市場調査部長・チーフアナリストである今関豊和氏は「渋谷区の上昇はペースダウンしている。意思決定の速い企業の解約がピークを超え始めており、それがペースの鈍化になっている。その一方、解約の動きは比較的大きい企業にも広がっており、(その現象は)港区で顕著に出やすい」と分析する。
大企業の戦略見直し
潮目の変化は大企業の動向だ。三幸エステートの今関氏は「コロナ以前には戻らないという判断。ニューノーマル(新常態)と言われる、テレワークなどをハイブリッドな形で入れていき、オフィスを組み立て直す必要性がある。現在のオフィスの物理的なサイズを大きいと感じるのは、アフターコロナを見据えても考え方は変わらない。そういう判断をしている大企業が増えている」と指摘する。
ただ、企業規模が大きいほど、実際のアクションに落とし込むまでには時間が掛かる。定期借家契約を踏まえると、その契約が切れるタイミングに向かって、オフィス戦略の再構築検討が進められる。在宅勤務、サテライトオフィスという選択肢が増え、組み立て方が複雑化。1人当たり床面積に加え、出社率から考えなければいけない現状で、従来以上に難しい〝方程式〟を解く必要がある。
市場の臨界点は
一般的にオフィス市場では、空室率が5%を上回ると、供給過剰になり、借り手市場になると言われている。この5%という数値はバブル経済のころから言われ始めたとされる。当時と現在ではオフィスの床面積の規模が格段に違う。4%でも過剰感が出るのではないかという意見も業界にはある。
三幸エステートの今関氏は「オフィス需要が上がれば賃料は上がりやすく、需要が下がれば賃料は下がりやすいもの。定量的に見ると、5%を上回る、下回るということで、賃料がフリップ(反転)するという感じはない」と説明する。新型コロナという原因がはっきりしており、長期的に影響を与えるものではないとすると、「過剰に悲観的になる必要はないが、どれだけ在宅勤務が広がるかが問題。(これまでの)統計モデルでは読み込みにくい不確定要素」と述べた。
東急 下降基調の中で旗艦物件は好調
渋谷区で再開発やオフィスリーシングに注力する東急(東京都渋谷区)。渋谷区のオフィス市況の厳しさが伝えられる中で、同社保有の物件では空室率はあまり上がっていないという。同社ビル運営事業部運営第一グループの福島啓吾主査は「この半年で退去もあれば、入居もある。全体のバランスでいけば、それほど危機的には見ていない」と述べる。「ヒカリエ」といった旗艦物件では、コロナ禍で成長を遂げている企業を中心に引き合いがあり、空床もこの6カ月間で入居の見通しを立てた。
区全体について、福島主査は「コロナ以前の空室率には異常な感じがあった。借りたいというお客様に貸せる床がなかった。当社保有の物件だけでなく、周囲を見回しても同じ状況。新しい企業を受け入れられない、増床の受け皿がないのは、マーケットとして健全ではなかったのでは」と振り返る。東京全体の賃料単価が上昇した際に、駅から遠い築古の小規模物件の評価も上がったが、そうした物件が現在、苦戦している。
日本経済や産業が苦しむ中で、同社は当然、ダウントレンド(下降基調)が継続すると想定。年度末に掛けて東京都内のオフィス空室率は上昇し、「ある程度、貸し手市場だったものが、借り手市場になる」(福島主査)という認識を持つ。
ただ、同社が顧客から得ている感触では、オフィスが必要という意見は根強い。ダウントレンドはコロナ禍よりも、不況対応の側面が強い。景気が回復すれば、テレワークを維持しながら、企業はオフィスに回帰し、需要も回復すると見ている。