不動産業はドメスティック(国内)産業の代表格といわれる。一部では、海外不動産投資や、海外でマンションや戸建て住宅を販売する動きも盛んだが、中小規模の不動産会社には限界がある。そのため、少子高齢社会の今、住宅・不動産業界では、「市場は縮小せざるを得ない」といった見方が一般的だが、本当にそうだろうか。
日本がこれから迎える超高齢社会は世界的にも類を見ない。例えば、総人口が減少傾向にある中で、高齢者(65歳以上)人口は増加トレンドを続け、その比率は50年には40%近くに達する。世帯構成を見ても、これまで主流だった「夫婦と子供」からなる世帯は50年には少数派になり、単身世帯が40%を占めて主流となる。このほかにも、60年には現役世代1.2人で65歳以上の高齢者を支えなければならないとの推計もある。
こうした情報はもはや〝耳にタコ〟状態で、国民はマヒしてしまっているきらいがある。
このまま国全体が〝ゆでガエル〟にならないためには、政府もそうだが企業も、今やるべきことを真剣に考えなければならない。高齢化も人口減少も単身世帯の増加も、その影響を真っ先に受けるのは地域社会だ。ということは、地域に根を張る地元不動産会社こそ、未来を切り開くビジネスを起こす必要があるだろう。
といっても、大げさに構えるのではなく、地元住民と日頃から接している中から、新たなニーズ、悩みを聞き取り、それを分析することでこれまでになかったビジネスにたどり着けると思う。
例えば、資金需要を抱えた高齢者の自宅をいったん買い取り、賃貸住宅として貸すことで、売主の高齢者がそのまま住み続けることができる「自宅のリースバック」は、長寿化の今、これまでになかった商品として関心を集めている。シェアハウスという居住形態もニッチな市場として捉えるのではなく、単身世帯が増える今後の社会では、地域を疲弊させない有力な手段として定着する可能性が考えられる。更に、これまであまり活用されてこなかった定期借地権付き住宅も、十分見直される価値があるのではないか。今後もマクロ的には地価の下落トレンドが続くとすれば、土地を所有しない居住形態は合理的だ。土地に回す分の資金を家族旅行や子供の教育費などに充てる利用価値重視の考え方であり、こうした選択肢は若年層から支持されやすいのではないか。地主側としても、今のようなゼロ金利時代ならば、地代利回りが1、2%見込める土地活用は魅力的だろう。
このように、課題山積の国内だからこそ、国内の隠れた需要、それに対応した新商品が生み出される可能性は高い。地域に根を張る中小規模の不動産会社は、それを強みと意識し、地元住民のニーズを掘り起こし、市場縮小を跳ね返す視点を持つべきだ。








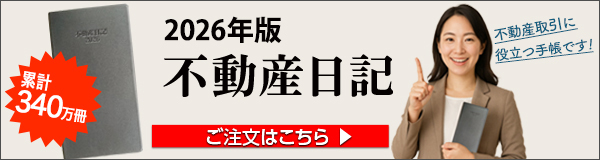






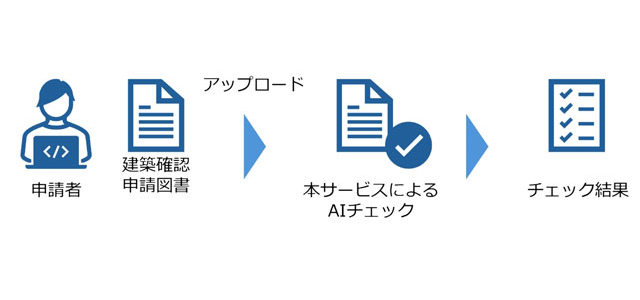
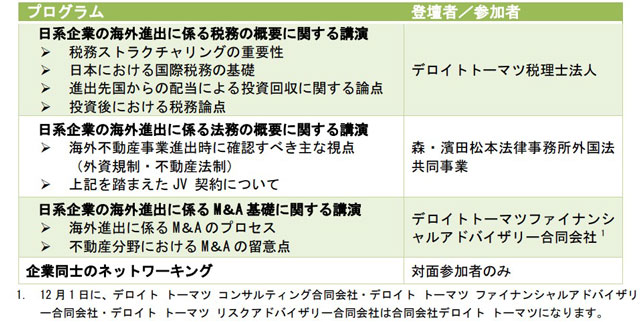



.jpg)
.jpg)