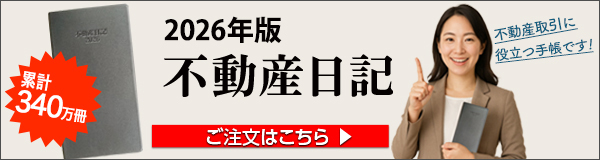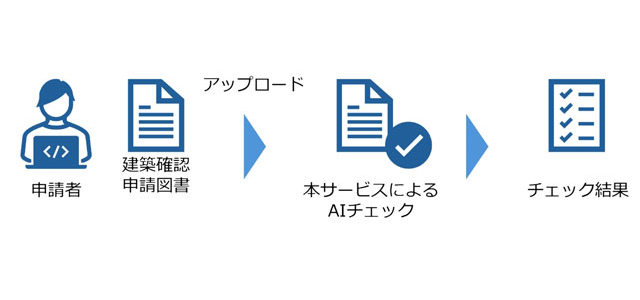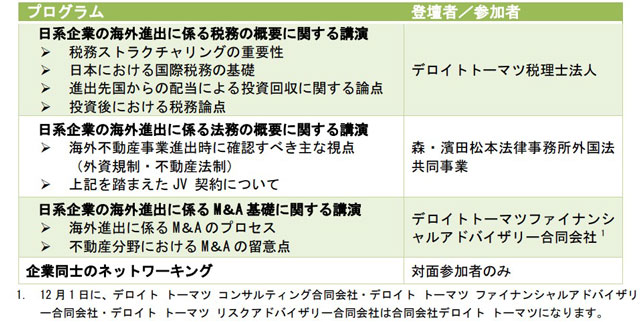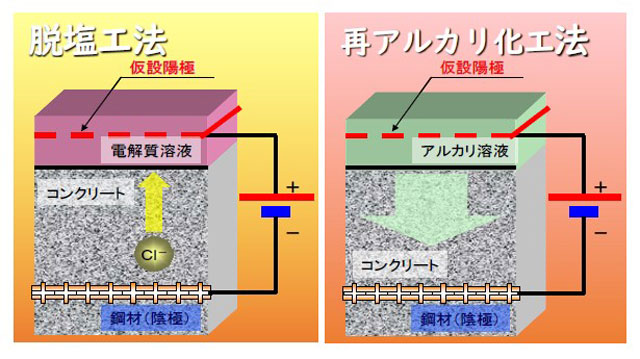岩手、宮城、福島の東北3県の太平洋沿岸を中心に、2万人を超える尊い命と、住宅や工場などの生活基盤の多くを奪い去った。その甚大な津波被害となお収束しない原発事故を引き起こした「3.11東日本大震災」から6年。「槌の音」高く、新しい町が見えてきた地域がある一方、放射能汚染の影響でまだ8万人が避難生活を送る福島県があるように、今なお厳しい現実を払いのけることができない。
多くの被災地の復興への足取りは、残念ながら当初計画より遅れているが、地元の「自分たちの手で」という強い思いと頑張り、そして国や県、関係機関などの支援で着実なものになってきた。
津波被災地の復興事業は難しい。流された町の将来像をどう描くか、高台移転の用地確保はできるか、更に権利関係の調整は――など難題が山積している。そうした困難を乗り越え、各地で災害公営住宅が出来上がり、経済活動の拠点となる水産加工場や新しい商店街が開業している。遅れ気味ながらも伝えられる被災地の着実な足取りは、多くの国民に大きな勇気を与えてくれている。
例えば、宮城県女川町。若者たちが立ち上がり、被災から丘の上に駅舎と商店街が出来上がるまでを描いたドキュメンタリー映画「サンマとカタール」(乾弘明監督)が昨年公開された。様々な葛藤を乗り越えて、震災翌年から始めた「復幸祭」では、「復幸男レース」が名物となった。津波の記憶を後世に伝える知恵であり、頼もしさが伝わってくる。
記録は共有の財産
こうした人間ドラマは恐らくどこの被災地もある。合意形成が難しく、復興への道のりはなお遠く長い地区も多数存在することも確かだが、大災害に襲われた経験、そこから復興へ向けて立ち上がった住民たちの取り組みは、必ずや人の命を守るヒントや助けとなる。それは東北の被災地域だけでなく、初めて帰宅困難者で道が埋め尽くされた首都圏での経験も同じ。それらは「人類共通の財産」として生かすことができる。
東日本大震災の後、我が国では南海トラフ地震、首都直下地震への警戒と対策の必要性が高まった。大都市部では建物の耐震化、不燃化を、沿岸部では津波対策が急務の課題として強化されてきた。だが、昨年4月、最大震度7が二度も襲った熊本地震が発生。残念ながら大きな被害を防ぐことはできなかった。
いつどこを襲ってくるか分からない大地震にどう備えるか。被災した場合の緊急対応、更に復旧復興をどう進めるかが問われている。人知を超える自然の脅威を見せつけた東日本大震災は、私たちに多くのことを教えてくれた。その経験を忘れず、事実を直視して次世代に着実に伝えていくことが求められている。