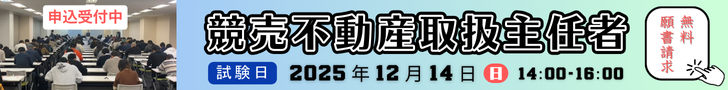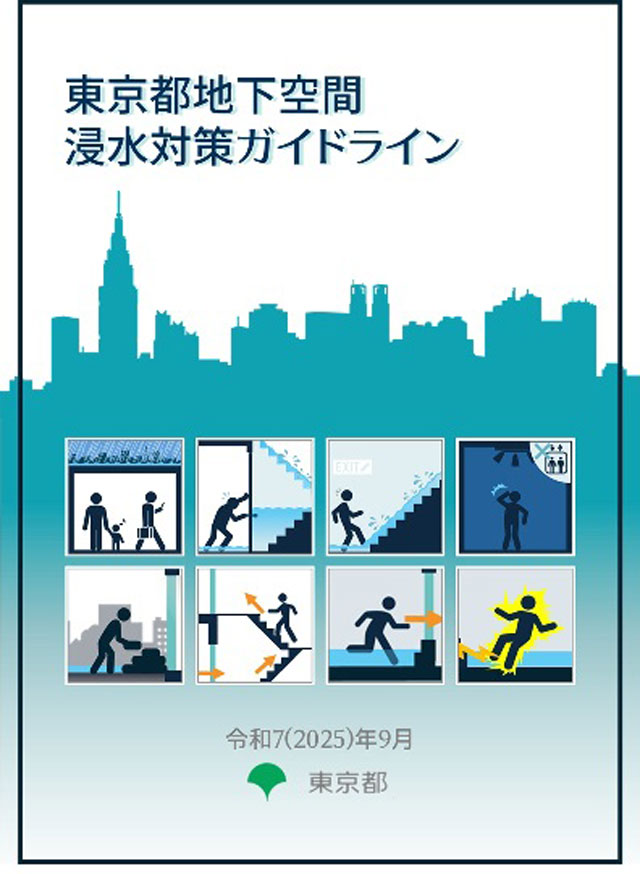地価上昇は全国的に広がりを見せ、その勢いはなお続きそうだ。国土交通省の23年第2四半期の地価LOOKレポートでも3期連続で下落地点はゼロ。社会経済活動の正常化と訪日客の回復で店舗需要が急回復しており、9月19日公表の基準地価(都道府県地価調査)もその傾向を映し出す可能性が高い。だが、「今の地価は高すぎる」と地場不動産会社の社長は苦笑いする。投資用不動産の価格は収益還元法に基づき決まる。その考え方で言えば利回りが取りづらくなり、資産デフレから脱してバブル懸念が頭をもたげている。地価高騰のみならず、建築コストがかさむなどで今年は坪単価1000万円超のマンション価格が話題をさらったのは記憶に新しい。
ただ、1980年代後半のバブル経済期とは状況が違う。例えば、バブル期は今よりもワンルーム系など狭小マンションが多く供給されたため、1戸当たりの平均専有面積は現在のほうが広い。供給場所もバブル期は全国どこにでも、という様相だったが、今は都市部に集中する。専有面積の広さと都市部集中が足元のグロス価格を引き上げているにすぎず、単価ベースで比較すればバブル期の8合目当たりで上昇余地を残しているとの指摘もある。確かにバブル期は坪2000万円超もあった。しかし、だからと言って、今以上に高額な物件を供給し、実需向けの住宅価格までつり上げてしまうことの違和感はぬぐえない。資産価値が上がるメリットを生かし、自宅を売却して住み替えを検討しても住み替え先が高額で、2つ以上の不動産を持っていないとできない相談だ。足元の高騰を喜ぶのは富裕層と資産家に限られる。
当時のバブル期と違うという観点で言えば、収入と働く環境もその一つである。失われた30年で個人の所得水準はじりじりと下げ、契約・派遣社員を経済市況に応じて企業が調整弁的に使うなどで社会に分断を生み出した。まじめにコツコツと働く一般人が住みたい場所に住みたい家を購入できない状況は明らかに健全ではない。
実需向けの供給で存在感を見せていた中堅デベはリーマン・ショックで多くが姿を消し、大手主導のマーケットが広がる。その大手を見ていると、住まいは、持てる人だけ持てばよいという姿勢を強烈に感じる。企業がもうけを追求するのは当然であるが、衣食住の中でも住宅は食と並ぶ生活の基盤である。結局は、住宅・不動産業界はどうあるべきかという哲学が問われている。
過去の不動産の値上がりを振り返れば都市再生がらみでお金を入れ、先に供給をつくり出すことが重要視されてきた。これでは国民の所得が上がってない中での用地急騰は誰も止められない。こうした状況に国は施策を打つべきであろう。住宅ローン減税などの対処療法にとどまらず、国民の生活を豊かにする所得倍増政策に本腰を入れてもらいたい。