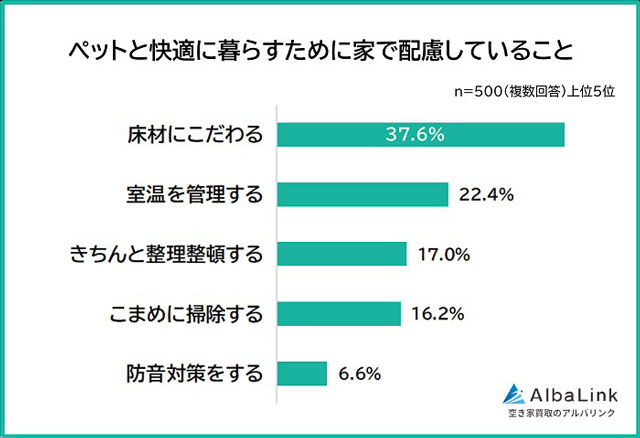パンデミックで不動産価格が暴落する懸念は杞憂に終わり、逆に東京23区の人気エリアはバブルと化している。新築時にタワーマンションを購入した個人投資家は、「4年前に1.2億円で物件を購入し、その住戸の評価額は現在1.8億円だ」と頬が緩む。東京都心ではこうした事例は珍しくない。
複数の投資家からも「白金や高輪は坪単価800万円。港区は4500万円が40m2台を購入する最低ラインだ」との相場感が聞かれる。しかし、この高騰ぶりに臆することなく売り物件が市場に出ればすぐに買い手が現れる。
なぜか。価格が上がり続けている様を見せつけられて「いま買わないと買えなくなる」(50代・女性投資家)からだ。キャッシュリッチが強いのはいつの時代も同じだが、価格になお上昇の余地があるという投資家たちのこうした心理はまさにバブルの象徴であろう。
日本銀行は緩和政策を維持する。10月31日に行われた衆院選は自民党が絶対安定多数を確保した。あふれる緩和マネーが資産価格を押し上げる構図は続き、これに便乗して売り主が価格をつり上げる。バブル狂想曲が続くほど宴が幕を閉じた後の谷は深い。
経験則から言えば、不動産会社などプロが市場形成を主導し、ファンド勢が存在感を高める。プロが作った不動産マクロ市況は個人の実需層の取引にまで影響を及ぼす。今や東京の新築マンション価格は平均年収の13倍に達する。
プロは事業として不動産を購入するのだからシナリオが全部できているが、足元では利回り3%台でも強気の姿勢で取引をする。バブル経済崩壊後に利回りから収益価格を割り出す収益還元法が定着したが、「先走りがちな取引価格を抑制する手段」という当初の発想は歴史的な低金利と外資勢の登場によってもはや通じない。
「ババを引くのは誰か」。そろり忍び寄る金利上昇の足音にプレーヤーは耳を澄ませる。金利上昇は取引現場を凍り付かせるためだ。米国では量的緩和の縮小を決めたが利上げを急がないとして金利の上昇に一服感が出ているものの、それでも「米国の金利は来年6月末までに2%になる」(証券大手)といった観測は消えていない。金利上昇局面はJリートの運用成績がベンチマークを下回るのも経験則だが、米金利動向が日本に波及することを代弁している。
そもそも借り入れに依存する不動産事業では名目金利と不動産の利回りギャップに着眼する。その利幅は薄氷を踏む思い。実物不動産で利ざやが薄くなるほど投資家が資金を一気に引き上げる公算は大きい。プロが勝手にヒートアップして早々に手仕舞いする繰り返し。分断社会下の実需層の視線は冷ややかだ。〝買える人だけ都市部で家を買えばいい〟という業界体質が透けると同時に国民の生活基盤である住宅市場に対する政策の脆弱性を不動産市場は映し出している。