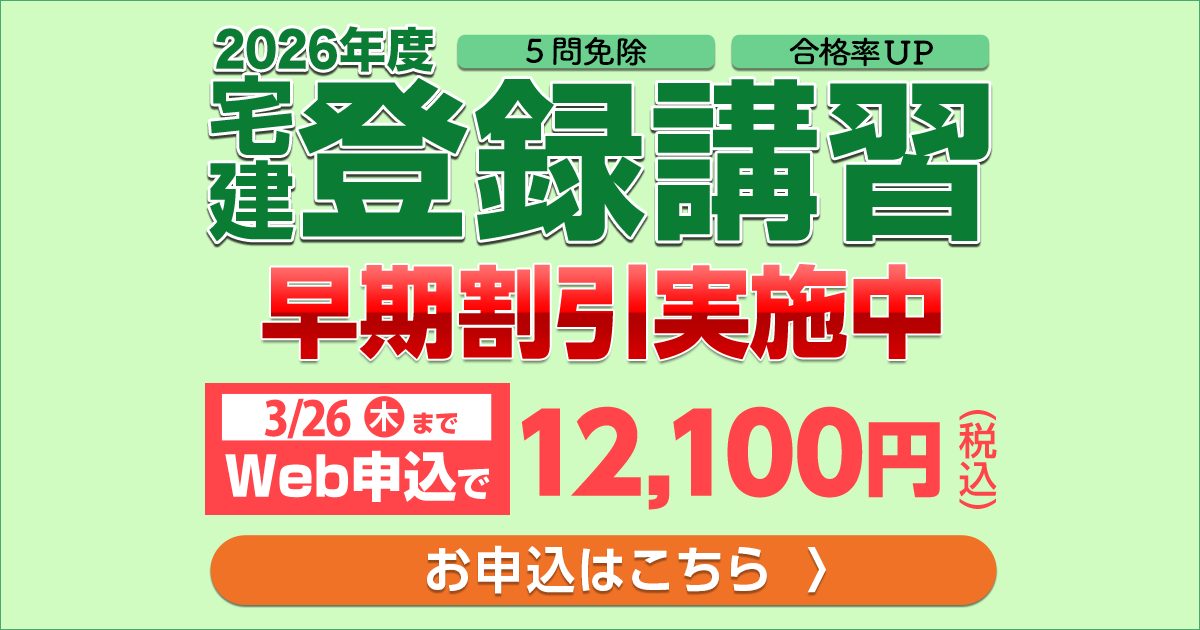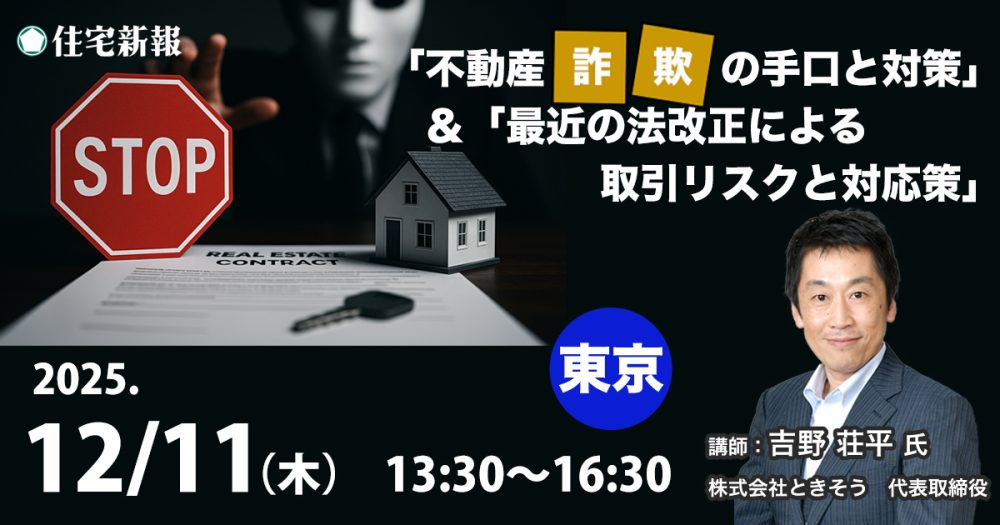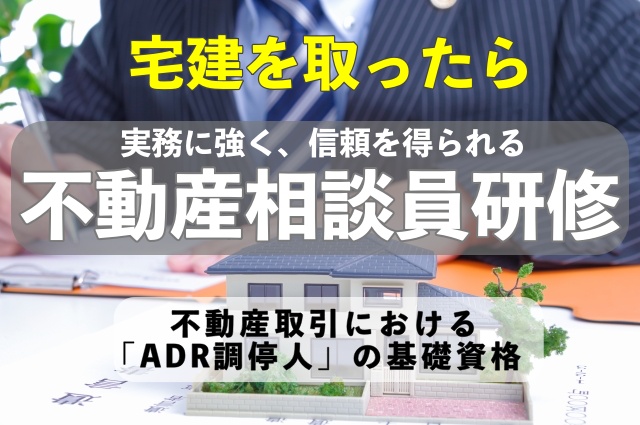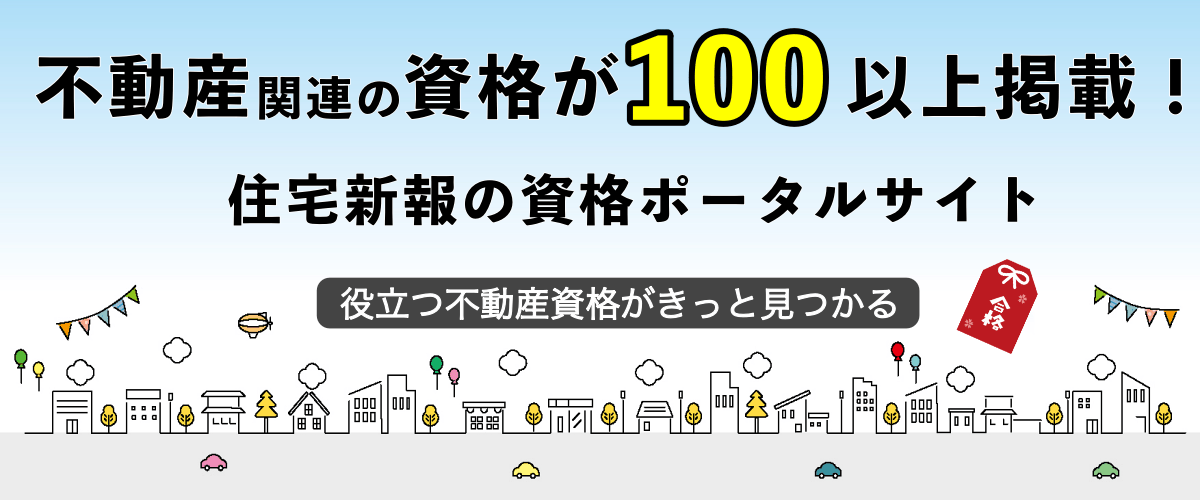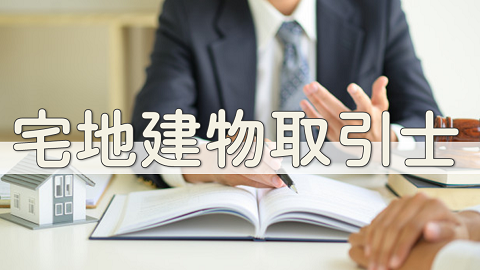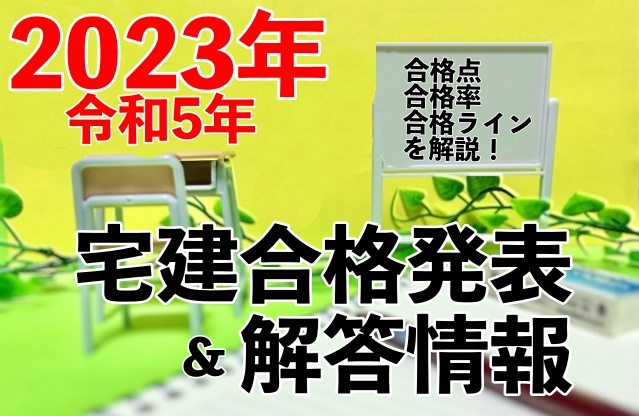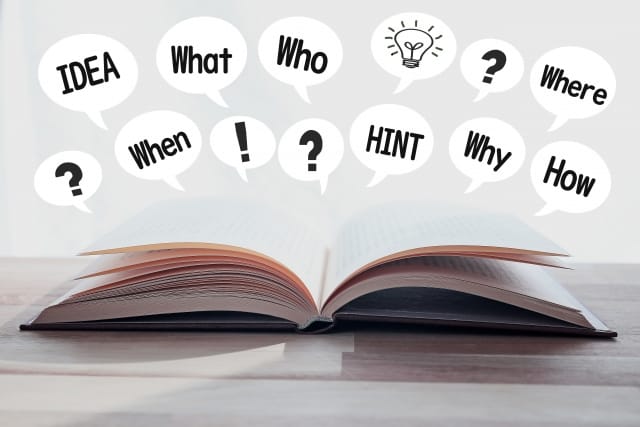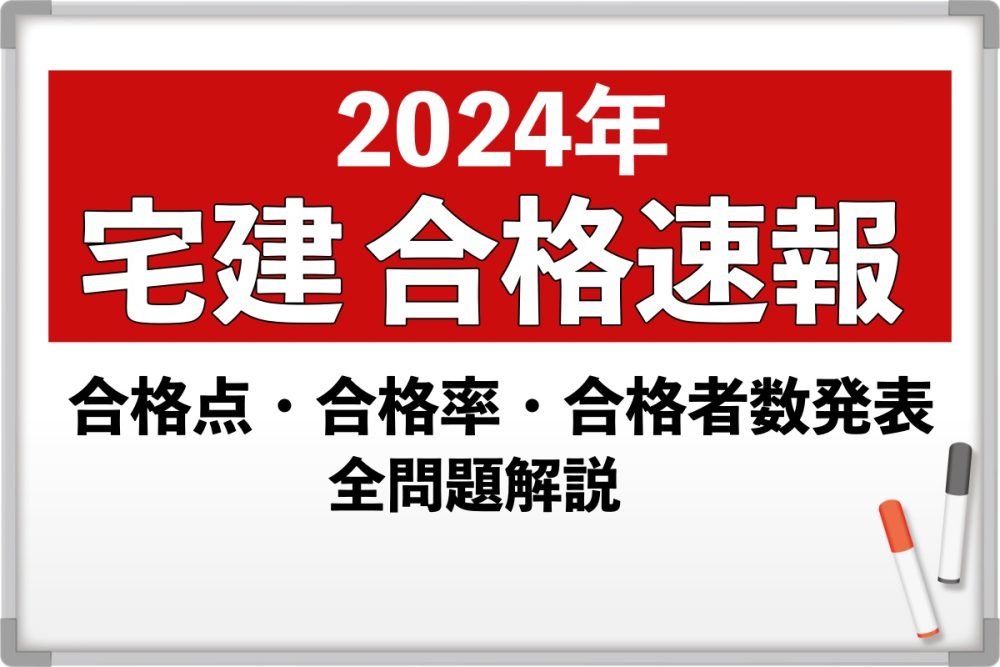『不動産・困ったときの知恵袋』〔第5回〕 地中の異物の存在は土地の瑕疵になるのですか?
〈不動産取引に関するお役立ち情報コーナー〉
地中の異物の存在は土地の瑕疵になるのですか?
困りごとの内容

以前このコーナーで、土地の売買での埋設管の存在は契約当事者の問題であって仲介業者の責任ではないという事例が紹介いたしました。
今回の事案は、売主が古家を解体した際に生じたコンクリート基礎の残骸や木片等のガラの混入事案です。
解体に伴う異物の存在は土地の売買においてはよくあることだといわれていますが、それらの存在が土地の「瑕疵」に当たるのかどうかについては、以前のこのコーナーでも詳しく触れていませんでした。
異物がコンクリート基礎の残骸と共同下水管という違いはあるのですが、何かその判断の基準になるような判例などはないのでしょうか。
解決のための知恵
買主に特に不利益を与えなければ瑕疵にはなりません 地中埋設物の問題については複数の裁判例があり、その中で今後のお役立ち情報として参考になるものがありますので、以下にご紹介します。
以前のこのコーナーで紹介されていた「隣地との共同下水管の埋設」のように、特に買主に不利益を与えるものではないというケースや、地中埋設物が買主にも利用できるようなものであれば必ずしも瑕疵にならないという裁判例(札幌地判平成17年4月22日、東京地判平成26年10月23日)があります。 また、地中の杭の存在がむしろ買主にとっても有益だと判断されたケース(東京地判平成15年12月1日)や、地中のわずかな幅の構造物の存在は瑕疵にはならないとされたケース(東京地判平成22年4月8日)などがあります。
それらの裁判例の考え方を1つにまとめた事例として、次のような裁判例があります。
「土地の売買において、地中に土以外の異物が存在する場合一般が、直ちに土地の瑕疵ということができないことはいうまでもないが、その土地上に建物を建築するについて支障となる質・量の異物が地中に存在するために、その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備・改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要とする場合には、宅地として通常有すべき性状を備えないものとして土地の瑕疵と認めるのが相当である(大阪高判平成25年7月12日)」
地中混入物の存在が「瑕疵」に該当するかどうかという判断基準については、2020年4月1日からは「契約不適合」に該当するのかどうかという判断をいたします。
本件の問題がいわゆる土地の「隠れた部分」における問題であるだけに、判断基準については基本的に従前のものと同様になります。
ただし、契約不適合責任に該当するかどうかの判断は、瑕疵担保責任の場合と違って、契約の当事者が合意した「契約内容」がどういうものかによって違いが出てくる可能性はあります。
契約不適合責任は2020年からの判断基準のため、詳細は今後の判例の蓄積を待つことになりますが、現段階で注意すべきことは、契約の際に「異物の存在」についても詳細に確認をしておくということになります。
このような内容は宅地建物取引士の試験では非常に重要な「契約不適合責任」で出題されます。
次の記事
>>『困ったときの知恵袋』〔第6回〕契約不適合責任の対応で仲介業者がまず行うべきことは?
前の記事
著者